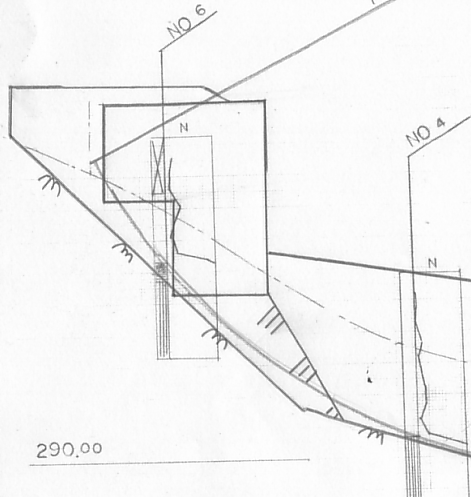 |
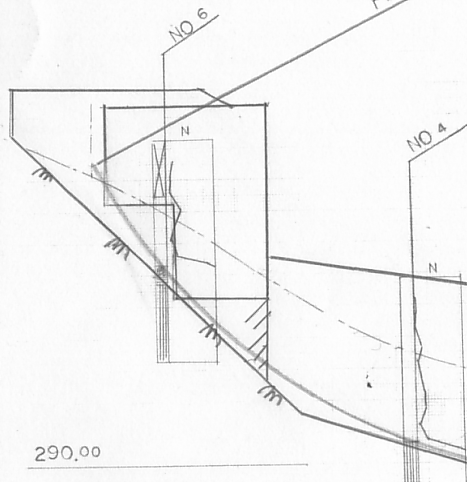 | |
| 図2-1(O鑑定計算) | 図2-2(横井鑑定計算) |
滋賀県某テールアルメ崩壊事故8(3rdRnd)
さて、そうこうしている平成14年8月の始め、今度は被控訴人Dから、工学博士にして技術士であるOによる「鑑定意見書」(以下O鑑定と呼ぶ)が、当方に送りつけられてきました。D社内だけでは拉致が開かず、とうとう他人に頼まなくてはならなくなったのでしょう。おかげで暫くの間、このO博士(白紙といっても構わないのですが)と、つき合わなくてはならない羽目になりました。
実は、O鑑定書は、どうも捨ててしまったかなにかで、現物が見つからないので、全文を示すことは出来ません(その内出てくるかも知れません)。但し、詳しいことは忘れていますが、肝心なことは憶えているので、要点だけをここで述べておきます。
1、鑑定人のO博士は確か信州大43年卒。工学部土木工学科環境システム工学専攻かなにかだったかと思う。本人は盛土の専門家を自負しているらしい。
卒業後川鉄建材(株)で補強土の研究・開発に従事。川鉄建材(株)退職後、(株)補強土コンサルタント代表取締役。何だ、要するにテールアルメ談合3兄弟の一人だったのだ。
2、O鑑定の要点は以下のとおりだったと記憶している。
先ず、過去の崩壊事例を挙げ、盛土が崩壊するのは連続降雨量が200数10㎜以上に達した時、特にテールアルメの崩壊事例は、降雨に関連したものが大部分を占めるとし、
1)テールアルメのクラックは地震によるものではなく、又、地震の影響では地盤にクラックが入ることはない。
2)崩壊の主因は、地すべり地上にテールアルメを設置した事にある。
3)地すべりを生じた誘因は、5月中旬以来の集中豪雨である。
4)(彦根地方気象台の観測記録から)この豪雨は、100年に一度あるかないかのものであり、基礎が砕石で置き換えられておれば、なお安定を保っていたと考えられる。
5)横井鑑定による安定計算は、安全率を不必要に過小評価している。我々の計算によれば安全率は7〜8%上昇する。
①横井安定計算はストリップの補強効果を無視した計算である。
②横井安定計算は砕石置換範囲をテールアルメ端部から直角に降ろしているが、通常は山型に傾斜させる。
その結果次の様になった。
(横井安定計算)
| すべり形状 | ケース | 無処理 | 砕石考慮 | 安全率増加割合(%) |
| 全体すべり (地すべり面) |
地下水位考慮 | 0.947 | 1.001 | 5.7 |
| 地下水位無視 | 1.371 | 1.433 | 4.5 | |
| 局所すべり | 地下水位考慮 | 1.001 | 1.163 | 16.1 |
| 地下水位無視 | 1.218 | 1.401 | 15.0 |
(O鑑定人安定計算)
| すべり形状 | ケース | 無処理 | 砕石考慮 | 安全率増加割合(%) |
| 全体すべり (地すべり面) |
地下水位考慮 | 0.94 | 1.01 | 7.4 |
| 地下水位無視 | 1.26 | 1.37 | 8.7 | |
| 局所すべり | 地下水位考慮 | 1.04 | 1.32 | 26.9 |
| 地下水位無視 | 1.31 | 1.68 | 28.2 |
この鑑定意見書には次の大きな特徴があります
1)かつて声高に叫んでいた、地震時での剪断クラックや、雨水浸透による地盤の強度低下理論は何処かへ行き、その変わり、雨の問題をクローズアップしてきました。平成7年5月降雨を極めて希な現象とし、それにより自己の責任を減殺する作戦でしょう。
2)地すべりは認めたのですが、本質を、砕石置き換えという、瑣末な問題に置き換えようとする意図は見え見えです。
さて、これに対し、先ず当方代理人(弁護士)から猛反発がありました。まず、それから紹介します。
平成12年(ネ)第3155・3156号 請け負い代金請求控訴事件
準備書面
平成14年8月
大阪高等裁判所第三民事部 御中
控訴人(第一、第二事件原告)訴訟代理人
弁護士 F ,Y 印
第一 Dの鑑定書(丁26〜37)に対して
一、始めに
「訴因はテールアルメを地すべり地に設置したこと、誘因は連続降雨量363㎜(最大日降雨量231㎜)の大雨に遭遇したこと。但し、連続降雨量232㎜及びその後の連続降雨量208㎜の大雨では崩壊しなかった」というのが結論である(丁17、P2)。
「過去の崩壊事例からも降雨による崩壊が最も多いことが判っている。崩壊に至らなくても、変形等現場で問題となったテールアルメにおいては、殆どが完成後の降雨によるものが原因となっている」(P1)とある。
素因・誘因という用い方は、不明確だが、すべり地と豪雨が原因というのは、まず、専門家なら共通に下す結論である。この点は、Oの鑑定は正しい。しかし、5頁以下については、明らかに誤った鑑定としか思えない点が多々あるので、その点について述べる。
二、鑑定意見批判
1、「以上より、平成7年5月の彦根における連続降雨は、100年に1〜2回程度の確率で発生する豪雨であったことが判る。なお、当該現場のある土山町では、彦根よりもさらに多量の降雨量があり、少なくとも彦根同様に100年に1回程度の確率で発生する豪雨だったことがわかる」(丁27、P6)とある。
O鑑定が、当該現場付近の土山町のデータではなく、彦根のデータを下に論を進めているのは、彦根には彦根地方気象台があり、1894年から現在までのデータが保存されているからと思われる。また、彦根地方気象台に頼んで入手したデータ(甲68)からしても、5月の降雨量としては、348.5㎜というのは、1894年以降1992年までのデータからして第一位であった。そしてO鑑定は、「平成7年5月に当該現場(土山町)に降った大雨の規模について調査した。統計資料については土山町ではなく、降雨量の少ない彦根のものであったが、彦根においてもこの100年間で最大級の降雨であったことが判った。彦根よりも相当降雨量の多い土山町でも同様に、この100年間で最大級の降雨であった」(同)と結論付ける。
しかし、この鑑定は完全に間違いである。O鑑定人は、5月が年間を通して最大の降雨月だと考えている。こんなことがないのは常識である。
2、1894年か1992年の99年間の彦根での月降水量(甲68)より、300㎜より多い月を挙げてみる。
1895年7月は501.8㎜、9月は1018.3㎜である。1897年9月は398.8㎜、1899年9月は377.7㎜である。
1903年7月は547.4㎜、1904年7月は358.4㎜である。1905年6月は433.2㎜、1906年9月は350.8㎜、1907年8月は358.8㎜、9月は339.1㎜である。
1915年6月310.0㎜、1916年6月は398.4㎜、1917年9月は401.0㎜、1918年9月は302.2㎜である。
1921年9月は495.4㎜、1923年6月は388.5㎜、7月は300.9㎜、1925年9月は304.9㎜。
1928年6月は327.7㎜、1916年6月は398.4㎜、1929年9月は309.1㎜、1930年7月は303.1㎜である。
1931年7月は328.4㎜、1935年9月は309.0㎜、10月は326.6㎜である。
1941年6月は328.9㎜、1945年6月は316.7㎜、10月は326.6㎜である。
1951年7月は349.2㎜、1952年7月は349.8㎜、1953年7月は460.9㎜、9月は353.0㎜、1954年6月は392.1㎜、1957年7月は443.5㎜、1959年6月は422.8㎜、9月は463.1 ㎜、1960年8月は303.7㎜である。
1961年6月は481.8㎜、10月は313.2㎜、1962年6月は346.2㎜、1965年6月は308.8㎜、7月は409.9㎜、9月は455.3㎜、1967年7月は301.4㎜、1970年6月は322.5㎜である。
1971年7月は441.0㎜、9月は377.5㎜、1972年7月は375.5㎜、1974年7月は336.5㎜、1976年8月は305.5㎜、9月は365.5㎜である。
1982年8月は301.0㎜、1983年7月は320.5㎜、1985年6月は385.5㎜、1986年7月は333.0㎜、1987年7月は355.5㎜、1988年6月は427.5㎜、7月は330.0㎜、1989年9月は 395.5㎜、1990年9月は377.0㎜である。
| 注;このような冗長な書き方では読みにくくて仕方がない。表形式にまとめたらどうか、と弁護士にアドバイスしたら、「裁判所向けにはこういう書き方でなければ駄目」と云われた。 |
数字をゴチックにしたのは、1995年5月の降雨量348,5㎜より多い月である。34回ある。少なくとも、348.5㎜以上の雨は99年間に34回、つまり3年に一回程度の割合で確実に発生するということである。
5月が年間での最大降雨月などではあり得ないことは、梅雨と台風という日本の気候を考えればすぐ判ることである。
3、O鑑定は、理科年表2002を引用しながら「(「日降水量100㎜以上日数」が)一ヶ月で0.05日未満ということは、彦根で日降水量100㎜以上の雨があるのは20年に1度も発生しないことになる。当該現場がある土山町では日降水量231㎜となっている。残念ながら土山町のデータはないが、表ー1(理科年表;気ー43)から推察するとこの降雨は何十年に1度でしか発生しない大雨であったと考えられる」(丁27、P6)と主張する。
しかし、100㎜以上の雨は5月にしか降るのではない。他の月も降るのである。現にO鑑定人の引用する理科年表2002は、7月0.1、8月0.1、9月0.2、年0.4と明記されている(同)。つまり2.5年に一回は100㎜以上の雨は降るのである。
専門家としてのこのような誤りには、愕然とせざるを得ない。
4、以上を踏まえると、「①当該テールアルメは地すべり地に設置したが、平成6年9月頃の連続降雨量232㎜、及び9月末の連続降雨量208㎜に遭遇しても崩壊しなかった。②当該テールアルメは、平成7年5月の連続降雨量363㎜(最大日降雨量231㎜)、及び6月、7月の大雨によって崩壊した。この5月の大雨がテールアルメの崩壊の直接的な原因となっているが、この大雨は100年に1回程度の確率で発生する大雨であった。③この場合、テールアルメの下に置換砕石を設置していれば安全率は7〜8%増加する。従って、平成7年5月の大雨に遭遇しても崩壊しなかった可能性は高いと考えられる。④この平成7年5月の雨さえ崩壊せずに乗り切れば、確率的に考えればほぼテールアルメの安定性はその後も維持されると考えられる。(1)」というまとめも、「一方、設計図通りの置換砕石を実施しておれば安全率は無処理より7〜8%程度上昇していた。従って、置換砕石をしておれば、平成7年5月の記録的な大雨に遭遇していても、崩壊しなかった可能性は高い。また、この大雨は記録的な豪雨であったことを考慮すると、その後も長期間テールアルメは安定性を確保している可能性は高い(2)」(丁27、p8)というまとめも誤りとなる。O鑑定によっても、今回程度の豪雨で崩壊するのだから、7〜8%の安全率の増加では、数年後には崩壊したとなるはずである。
| 注(1)、(2) | 実を云うと、O鑑定書で、この下りを幾ら読んでも、意味を理解出来なかった。(1)に出てくる、”乗り切る”という言葉は、通常ある意志を持って、逆行的状況にうち勝つ場合に用いられる。この表現だと、何かテールアルメが、ある種の意志を持って、災害に立ち向うことが出来るように見える。誰が考えても、テールアルメは、ただの土の塊だ。魔人ゴーレムじゃあるまいし、テールアルメが自分の意志で、豪雨に立ち向かうわけがない。殆ど、オカルトの世界。しかし、土木屋は意外に、こういう曖昧な表現をよく使う。特に国交省の河川屋に多い。筆者が連中と、あまりウマが合わないのこのせいか? (2)は相対値を絶対値とすり替える、典型的官僚答弁。今年の年金問題でも、この手の誤魔化しが、あちこちで使われていました。古くは、例の所沢ダイオキシン騒ぎで、住民側が主張したのもこの類です。 |
5、O鑑定にはさらなる本質的な誤りがあると考えられる。①
(1)O鑑定では、全体すべり(本件は小規模ながら全体すべりである)の場合①地下水位考慮では、無処理の場合0.94、採石置換の場合は1.01で安全率が7.4%増加し、②地下水位無視では、無処理の場合1.26、採石置換の場合1.37で安全率が増加するので、平成7年5月の大雨に遭遇しても崩壊しなかった可能性は高い(丁27、P7〜8)というが、その主な理由は「当該テールアルメは地すべり地に設置したが、平成6年9月頃の連続雨量で232㎜、及び9月末の連続雨量に遭遇しても崩壊しなかった」というにある。しかし、事故前数年間の降雨量やそれから考えられる地下水位などを全く無視したもので理由として薄弱である。
本件置換採石は、本件テールアルメが設置された場所が地すべり地であることを前提に、置換採石の指示を行ったものではない。全く地すべり地であることを考慮していなかった。
Dらが加わって作成された補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアルでは、地すべり地にテールアルメを施工してはならないと明記されている(甲48、P28)。そして、D(C)は安全率を常時1.5、地震時1.2としてテールアルメを設計した。また、この1.5、1.2という数値は、一般に要求されている数値である。しかるにO鑑定人によれば、砕石置換をすれば常時(地下水位無視)1.37で、非常時(地下水位考慮)では1.01である(丁27、P7)。1,5、1.2を満たしていない。本件テールアルメを地すべり地に建築し、安全率1.5、1.2を満たしていなかった。だから本件テールアルメは砕石置換の有無にかかわらず崩壊したのである。これ以上のことは云えないはずである。土木構造物においては、最終安全率が必要安全率を満たしているかどうかのみが問題になるのであって、中間過程での安全率増加割合などは何の意味ももたないことは土木技術者として自明である。
地すべり地に建築したこと、安全率の計算を誤ったこと、いずれも明らかに設計ミスである。
(2)「施工者が設計図どおり、『テールアルメ基礎は岩着ないし岩に達するまで砕石による置き換え処理をする』を厳守して施工すれば、いくら掘削しても岩盤が出てこない状況に遭遇する。当然ながら計画とは異なる現場状況を、施主や施工管理者に報告する義務があった。もし報告しておれば、そこで再検討する事になり、今回のような崩壊には至らなかったと主張するが、原告現場代理人F.Tは、本件テールアルメの北側部分(3)の中央部を砕石で置き換えした際に、2m以上掘っても岩が出てこなかったので、Cの現場責任者B.Yに相談したところ、これ以上掘削し、砕石置き換えしなくても良いといわれた経緯がある(原審13回同人証人調書31丁〜33丁など)。だから、本件では、指定されただけ砕石置き換えをして、Cの指示に基づき、それ以上やらなかった可能性が非常に高い。
*(3)これは代理人の記憶違いで、砕石置き換えを省略した箇所は、本件テールアルメの”北”側ではなく、”東”側
だから、「結論的には、地すべり地に設置したテールアルメが、記録的な大雨に遭遇し、崩壊したわけであるが、控訴人A建設が設計図どおりに施工しておれば、その時点で有功な対策が施され、今回のような崩壊に至らなかったと考えられる。」とあるのも間違いである。
しかし、何よりも岩盤まで8mあるとして、そのような箇所にテールアルメを建築するよう設計したことこそが問題で、ボーリングを一本打つことをしなかった点設計ミスがある。
6、O鑑定は、設計段階で本件崩壊地にボーリングすべきであったかどうか、本件崩壊地は岩着しているか否かについて簡単に判断できるのか否かという肝心な点で、意見が述べられていない。
雨の件は、弁護士が十分述べている(このためにわざわざ彦根まで行ったらしい)ので、私はあまり口を挟まずに、O鑑定人の安定計算についてのみ反論することにしました。
O工学博士の安定計算は正しいか?
鑑定人 技術士(応用理学) 地すべり防止工事士 横井和夫
1,始めに
土木というものは理論と現実が一致しなければ何の意味も持たない、という技術体系である。理論的にいくらすぐれていても、それが施工不可能であったり、それ自身が一般市民や構築に当たる作業員に対し、危険性を伴ったり、経済的効果を生まないものは、存在意義が認められない。これは土木のイロハである。今回被控訴人Dの鑑定人として現れた、工学博士O氏が実施した安定計算を見ると、その点で、土木の基本を忘れたバーチャル計算に過ぎない感を強く受けた。いやしくも学位保持者が、このような誤りを侵しては、我が国の土木技術に対する信頼感を損ねるおそれがある。従って敢えてその誤りを正すことにする。
2、計算モデルの違い
当鑑定人とO博士との計算結果の差を次表に示す。
(鑑定人計算結果)
|
すべり形状 |
ケース |
無処理 |
砕石考慮 |
安全率増加割合(%) |
|
全体辷り (地すべり面) |
地下水位考慮 |
0.947 |
1.001 |
5.7 |
|
地下水位無視 |
1.371 |
1.433 |
4.5 | |
|
局部すべり |
地下水位考慮 |
1.001 |
1.163 |
16.1 |
|
地下水位無視 |
1.218 |
1.401 |
15.0 |
(O博士計算結果)
|
すべり形状 |
ケース |
無処理 |
砕石考慮 |
安全率増加割合(%) |
|
全体辷り (地すべり面) |
地下水位考慮 |
0.94 |
1.01 |
7.4 |
|
地下水位無視 |
1.26 |
1.37 |
8.7 | |
|
局部すべり |
地下水位考慮 |
1.04 |
1.32 |
26.9 |
|
地下水位無視 |
1.31 |
1.68 |
28.2 |
両者において、傾向として殆ど違いはない。特に全体すべりに対しては、O博士の計算結果(以下O計算と呼ぶ)に対し、当鑑定人の計算結果の方が、被控訴人Dに対し有利な結果となっている。唯一O計算が有利なのは、局所すべりに対してのみである。これは念のため行ったものであり、実際に生じたテールアルメ崩壊に対しては事実上意味を持たない。又、O博士は安全率増加割合を考慮しているが。これは現実には何の意味も持たない。土木構造物においては、最終安全率が必要安全率をクリアーしているかどうかのみが問題になるのであって、中間過程での安全率増加割合などは何の意味も持たないことは、土木技術者としては自明である。
特にテールアルメ設計マニュアルでは、必要安全率は常時1.5となっている。O計算でもこれをクリアーするのは、局所すべり砕石考慮のケースのみである。又、この必要安全率は、そもそもテールアルメ関係業者が、自主的に設定したものである。即ち、被控訴人Dは、自ら自主管理基準違反を犯している。その点について被控訴人D並びに鑑定人であるO博士はどういう説明をするのか、是非聞かせて頂きたい。
しかし、計算結果においてこういう差が生じた原因は、今後の審理を左右する可能があるで、この点については吟味する必要がある。
この違いは大きく次の二つが考えられる。
1、ストリップの引っ張り強度を考慮するか否か。
2、砕石置換範囲の設定
1、ストリップの引っ張り強度を考慮するか否か。
補強土工法を併用した盛土の安定計算では、補強材の引っ張り強度まで考慮するか否かについては、従来意見が別れる処であった。本件テールアルメ設計時点ではこのような方法は未だ一般化されていなかった。しかし、現在では、平成11年度「道路土工」の改訂により、補強材効果をとりいれるのが通常である。小川安定計算はこの考えに基づいていると考えられる。これ自身は合理的であるが、実際を見ると殆ど効果は生かされていない。つまり安定計算書を見ると、すべり面(安定計算で算出された安全率最小の面)は何れもテールアルメ背面を通っており(丁32号証P2〜8)、テールアルメ補強材効果があるとは云えない。
2、砕石置換範囲の設定
当鑑定人の安定計算と、小川安定計算の最大の相違はこれであろう。砕石置換範囲については、双方において次のような相違がある。
O博士は図2−1のようなモデルを使用している。 一方、当鑑定人の用いたモデルは図2−2の通りである。
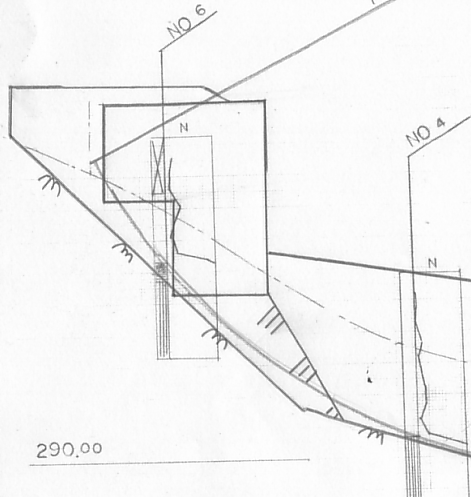 |
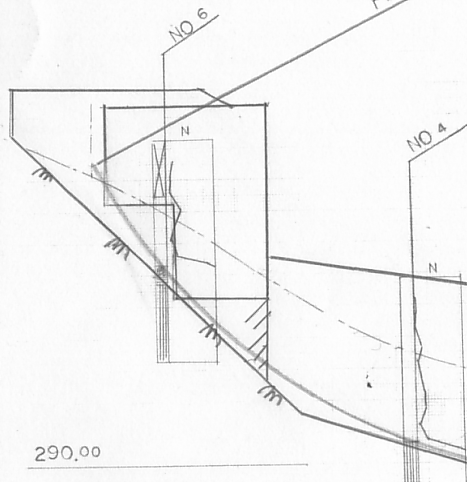 | |
| 図2-1(O鑑定計算) | 図2-2(横井鑑定計算) |
では何処がどう違うのか。O安定計算では、砕石置き換え部を正勾配(下に行くほど幅が広くなる)としている。これでは安定計算上、安全率が大きくなるのは当たり前である。しかし、このような断面が現実に可能なのか。下向きに断面を拡大して掘り下げることなど出来る筈がない。トンネル坑口対策工で用いられる補助工法を駆使して、地山を縫いながら断面を確保しつつ掘り進めなくてはならない。これは特殊工法であって、誰でも出来るというものではない。どのような施工をすれば良いのか、被控訴人D並びに鑑定人であるO博士の見解を是非伺いたい。(1)
なお、この件に関しては単なる文章ではなく
1)施工手順を示した図面を明示すること(マンガでは駄目。管理技術者…当然技術士でなくてはならない…の押印がある正式の設計図書)
2)仮設に要する構造計算書、数量計算書、工法比較検討書(同上)
3)安全管理計画書(同上)
を提出されることを要求する。
一方、当鑑定人安定計算では、砕石置き換え範囲を、テールアルメ外側から垂直におろしてある。これの意味は次の通りである。
前述のように、砕石置き換えを正勾配で施工することは不可能だから、通常は下図のように逆勾配で切り下げ、その中を砕石で置き換えることになる。
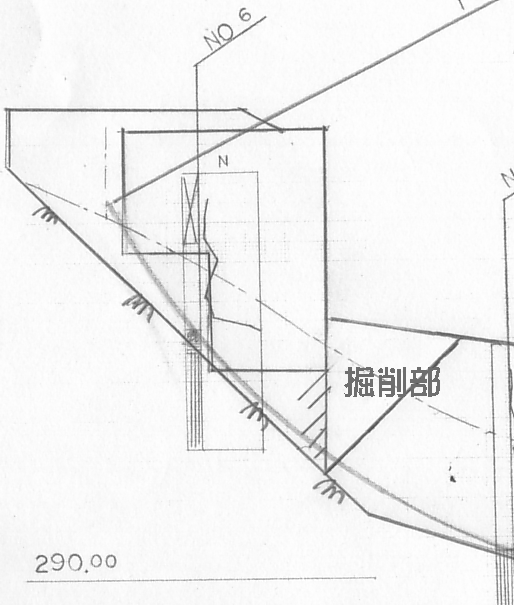 |
この場合の法面勾配は、「労働安全規則」の面から見て平均1:1.0が常識であろう。つまり、崩積土の厚さを8mと見込むと、必要掘削幅は、テールアルメ外側より8mの範囲になる。これは馬鹿にならない数字である。必要土工量から見ても、単なる基礎置き換えでは済まず、別工事として発注されるべき性質のものである。
当鑑定人としては、砕石置き換え部を、土工で処理すれば、掘削量が過大になると判断されたため、テールアルメ外側に仮設矢板を設置し、垂直掘削によるものとした。これでも8mに及ぶ掘削は容易ではないが、幸い山側は岩盤なので、これに支保工を設置することにより、施工は可能と考えられる。但し、支保材は仮設であるから、これの抑止力を、永久構造体である、テールアルメ盛土の安定計算に流用することは許されない。従って、剪断抵抗力は地盤強度のみを用いているのである。
被控訴人Dは本件テールアルメ詳細設計を請け負っており、且つ砕石置き換えは設計条件であるから、当鑑定人としては被控訴人Dに対し
1)置き換え必要範囲の明示(平面、断面)
2)置き換え工法の明示(工法手順の詳細)
3)同上数量計算書
の提出を要求する(2)
3、まとめ
以上述べたことは、工学博士Oによる鑑定書に対する反論の一部である。全般を通じて感じたことは以下の通りである。
1、O安定計算は非現実的なモデルに基づいており、その結果は考慮に値しない。
2、降雨強度の評価も恣意的であり、現実を無視している。
3、被控訴人Dはこれまで、地盤のクラックや浸透水による土砂流出を主張してきたが、小川鑑定ではその点には一切触れられていない。従来の主張は取り下げたのか。態度を明 確にすべきであろう。とにかく、被控訴人Dの主張は首尾が一貫していない。卑怯と呼ばれてもやむを得ない。
4、O博士に関しては、どうも中学・高校レベルの物理が理解出来ていないようである。この際学位を返上して中学校レベルから理科を勉強し直すことをお勧めする。
注(1);これは、O氏がテールアルメ屋で、トンネルなどの特殊工法の素人だろうと判断されたことによる、一種のブラフ。縫地など、やらなくてオープン掘削で構わないのだが、掘削断面を相手に描かせて、その過大断面ぶりを、裁判所に見せることが目的。さすがに相手はそれに気付いたか、無視してきました。
注(2);なお、こちらが要求した設計資料は、とうとう提出されませんでした。しかし、この鑑定書は非常に大きな意味を持っています。つまり、被控訴人Dが従来主張していた、阪神大震災によるクラックや、水の浸透による剪断強度の低下や地耐力の低下という理論は取り下げ、こちらが主張してきた地すべりを認めた訳です。Dとしては背水の陣といった処でしょう。だから可哀想なのは他の被控訴人。これまでDの云うことを頼りに不整形段差や剪断クラックなどと云ってきたのが、突然Dがそれを取り下げたから、どうしていいか判らない。Dの行為は当に自分可愛さだけの、敵前逃亡と云われても仕方がないでしょう。こんな節操のない会社の製品を買う気がしますか!これ以後、裁判所は、BやCの云うことに耳を貸さなくなったらしい。