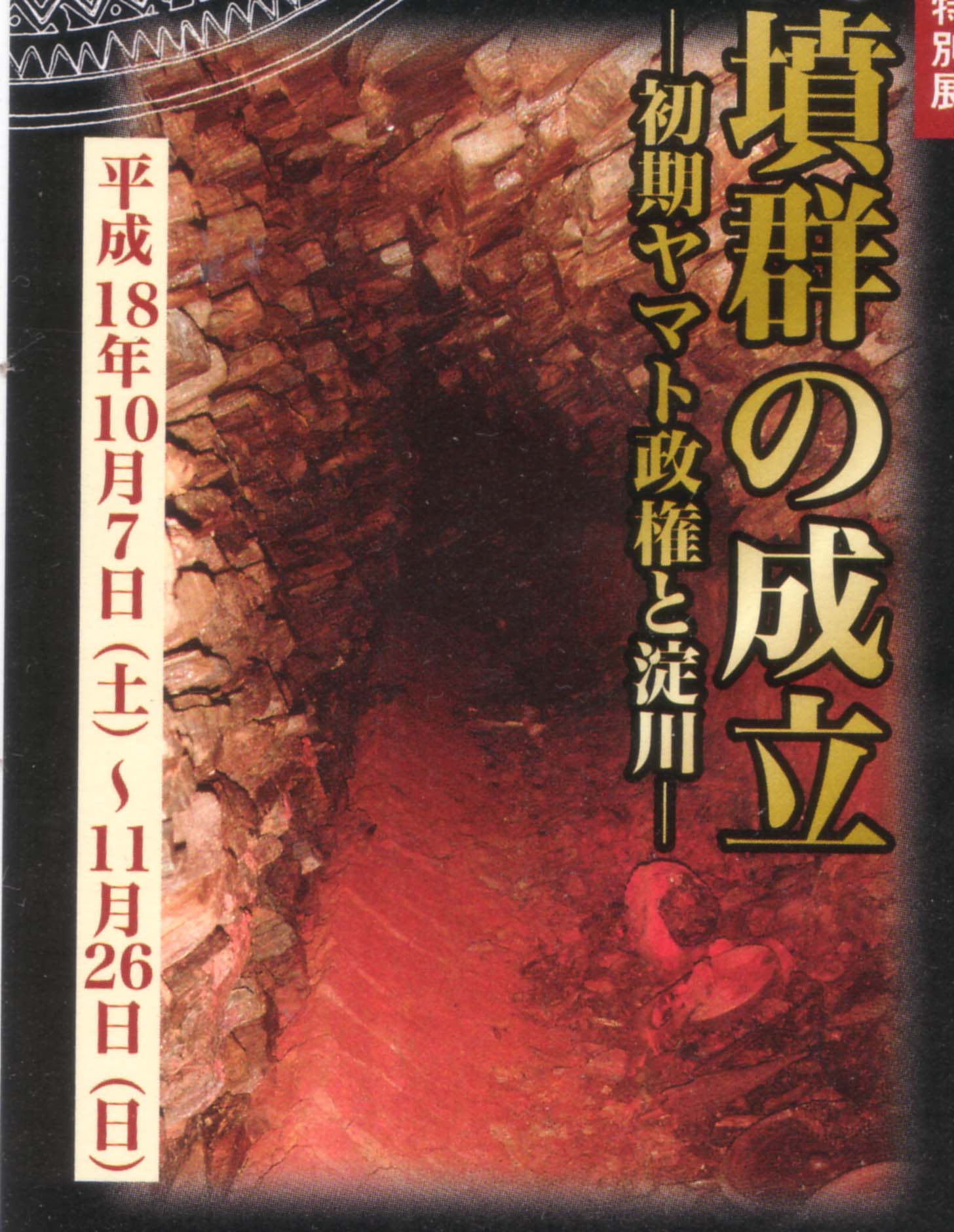 |
闘鶏山古墳と水銀、地下水
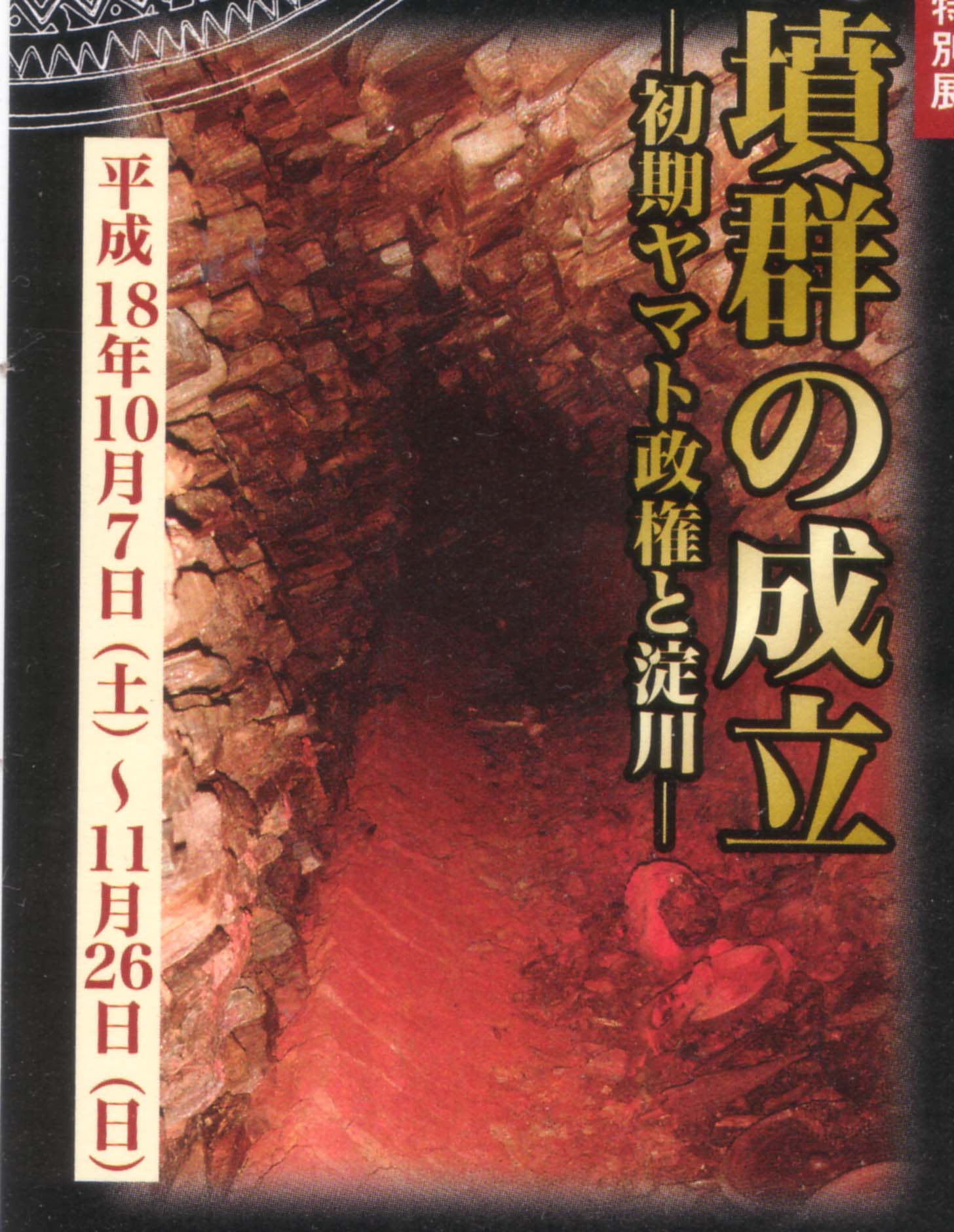 |
現在、高槻市「しろあと歴史館」である展示が行われています。その中に「闘鶏山古墳」石室のファイバースコープ映像がありました。無論それを撮影するわけにいかないので、とりあえず入場券で代用します。上の図は古墳石室映像2枚の内の1枚です。ここで次の2点に注目して下さい。
1)石室底部が嫌に赤い。
2)石室に水が溜まった形跡がない。
1)石室底部が嫌に赤い。
この赤さは「朱」、つまり酸化水銀の赤です。朱は古代では高貴な色とされたと云われます。本古墳の被葬者も、貴人の女性と云われますからそうかもしれません。しかし、実際はそれほど単純なものだったのでしょうか?後に述べる、石室内に地下水が浸透していた形跡が無いという点を合わせると、何か被葬者の保存技術に関係があるのかも知れません。
さて、問題は水銀です。この水銀は一体何処から来たのでしょうか?本古墳の築造年代はおおよそ4世紀前半とされる。その頃の日本に於ける水銀産地は、ヤマトと出雲、それに南九州が挙げられます。ここでいきなり、テーマは神武天皇(或いは応神天皇)に移ります。今のまともな日本人で、神武(応神)天皇という人物が実在したと考える人はまずいません。しかし、神武(応神)天皇になぞらえられる、外国集団の渡来の可能性を考える人は少なからずいるのです。古くは江上波夫博士の北方騎馬民族説があります。現在これはかなり旗色は悪いようですが、その他南方渡来説もある。少なくとも古代のある時期に、ヤマト(広義)に割拠していた諸部族が、後のヤマト政権となる、ある勢力に統合されていったのは事実のようです。これをとりあえずジンム族と呼びましょう。問題は彼等が何故ヤマトに侵攻してきたか?です。
記紀によれば、九州を発したジンム族は、広島・岡山を経由して、ナミハヤの渡しを越え(これから、彼等は船で水上を移動してきたことが判る)、河内のシラカタからヤマトに侵入しようとしたが失敗し、紀州に移動して紀ノ川河口から侵入しようとしたがこれにも失敗し、紀伊半島を迂回して熊野川を遡行して、南からヤマトに侵攻したのである。熊野川沿いは今は国道が通って自動車で楽に新宮まで行けるが、道のない時代の熊野川を想像出来ますか?本宮までは船で遡行出来るが、その上流は急流になるので、河原を徒歩で遡行することになる。両岸は切り立ったような絶壁の連続。無論、人が通れるような道はない。最大の難所は、標高1000mを越える天辻峠越え。ここは現代でも、トンネルが出来るまでは、冬季には交通止めになった。これほど彼等はヤマト侵攻に執念を燃やしたのである。と言うことは、ジンム族はヤマト侵攻に明確な目標と、入念な準備・計画をもっていた侵略者で、単なる移動者ではなかった、ということなのである。彼等は単なる土地ではなく、もっと付加価値の高いものを求めて、ヤマトにやってきた、としか考えられない。当時の日本が外国に輸出していたものなど、殆どありません。人口も大したことはない。つまり、産業や奴隷を狙ってきたわけではない。唯一考えられるのが、水銀なのです。当時、・・・と言っても何時のことか判りませんが、紀元5〜6世紀前後あたりにしておきましょうか・・・中国では黄金文明が花開いており、金の需要は盛んだった。中国周辺諸民族にとって、中国との交易ほど儲かるものはない。ところで金は、金単独で自然界に存在しているわけではありません。金は金鉱石という形で産出します。これを精錬して、金を抽出するわけです。この技術が狭い意味での錬金術です。金の精錬に不可欠な物質は水銀です。金鉱石と水銀を混合加熱して水銀アマルガムを作り、更に加熱して水銀をガスにして飛ばすと、後に金だけが残る。無論、金を銀に置き換えても、同じ現象が起こります。これは中国だけではなく、インド・ヨーロッパ錬金術でも同じで、その結果水銀は、錬金術つまり魔術の世界では、特別の地位を与えられることになります。その為古代世界では、水銀は金と同じ価格で取引されたと云われます。東方の海の向こうのある処で、水銀が沢山取れるという噂を聞いて、これを手に入れようと考える集団があっても不思議ではない。これがジンム族です。ジンム族は様々な情報網を使って、出雲・ヤマト・九州の三カ所に水銀産地があることを突き止めた。しかし、出雲・九州には既に強大な勢力があって、俄には手が出せない。それに比べ、ヤマトは豪族がバラバラに割拠して、一致団結していない。やっつけるならこっちだ、というわけでヤマトにやってきた、と私は考えています。ジンム族の侵攻ルートについては「基礎と地盤」を参照。では水銀産業は成功したのでしょうか?あまり上手くいかなかったと思われます。何故なら、古代で、日本から大量の水銀が、海外に流出したという話しは聞いたことがありません。あるにはあったが、鉱脈規模が小さく、採算に合わなかったのでしょう。ジンム族の親分は、一儲けに失敗して、仕方がないから、天皇になってしまったのではないでしょうか。だから、古代日本での水銀は、金の精錬用ではなく、別の使われ方をしたと思われます。水銀は常温で液体ですが、同時に昇華してガスを作る。これは猛毒で、殺菌・殺虫作用がある(勿論殺人も)。石室内は湿度が高く、恒温で、紫外線があたらない。こういう環境では嫌気性バクテリア(つまり黴)が繁殖しやすい。水銀ガスによってバクテリアの繁殖を防いだとも考えられます。
2)石室に水が溜まった形跡がない。
近くにいた案内員に、「ファイバースコープを挿入したときに、石室内に水はあったか?」と質問すると、「水はありませんでした。湿度は98%」という返事。そこで、「この写真をよく見なさい。仮に過去に水が溜まっていて、今偶々水位が低下したという見方もあるかも知れないが、側壁には水位が上下降した形跡がない。石室底面は凹状だが、水が流れたり、泥が溜まった形跡がない。これは、過去に水の浸透が無かったという証拠だ。1000数100年も風雨にさらされたのに水が浸透してこない。それは何故か判るかね」と質問すると、「古代の優れた技術」、などと曖昧で抽象的な答えしか返ってこない。賢明なる皆さんはこの理由はお分かりになると思います。判らない方は下の記事の内、3、前方盛土の成層構造を参照して下さい。
さて、要点は古代墳丘は大きく、内部の不透水層とその外側のランダム材、最外部の葺き石の3層構造からなっていることです。これが、石室内に水を一滴も入れなかったことの秘密です。それぞれの役割は何でしょう。不透水層は、透水係数が10-6〜10-7㎝/sec オーダー以下の材料で、ランダム材から浸透してきた水を、ここで遮断する役割を持っています。アースダムなどはこれが無いと、提体積が莫大になったり、提体からの漏水が多くて、水が溜まらなくなったり、最悪は破堤という結末に終わることがあります。一般には細粒分(粘土・シルト)を一定以上含む、大雑把に云えば粘土っぽい土です。ところがこの種の土は、含水比が高く施工性が悪い、扱いが厄介な土です。しかも表面に置くと、直ぐに乾燥して収縮クラックが発生して、強度が激減するなど、管理上も問題がある。つまり、性質が一定しない不安定な土だということです。そこで、より安定な土で表層を覆う必要が出てきます。これがランダム材です。これは透水係数が10-3〜10-4㎝/sec オーダーで、土性的には粗粒の砂や礫を主体とする土です。これは性質が安定しており、施工もしやすい。ところが水の浸食に弱いという弱点があります。斜面では、雨によって雨裂、ガリー浸食が発生しやすく、斜面はボロボロになってします。そこで葺き石の登場です。葺き石で表面を覆うことによって、ランダム材の流出を防ぐわけです。現代で云うロック材です。但し、葺き石は河原の玉石を使うので、石と石との間にどうしても隙間が出来る(例え間を粘土で充填しても、長期間には石は表面に沿ってずれるので、隙間の発生は防げない)。雨が降ると、雨の大部分は葺き石表面を伝って、外部に流出するが、一部は葺き石の隙間からランダム材の中に浸透する。ところがその奥に不透水層があると、そこから先は浸透出来ないから、雨水はランダム材を通って外部に流出するのです。ところが、雨量が多いと、ランダム材だけでは、浸透水を吐ききれないケースが出来ます。その場合は、ランダム材の中でパイピングを起こし、葺き石ごと崩壊してしまいます。これを防止するためには、常時のメンテナンスが必要です。しかし、王家の権威、財力が無くなると、ほったらかしになり、結局は崩壊するのみ。ところが、ここが温帯モンスーン地帯の絶妙の自然のバランスが発揮される。何処から風に乗って草や木の種子が飛んできて、葺き石が崩壊した後のランダム材表面に活着します。それが何年か繰り返されると、あとはしめたもので、次々と緑化域が広がり、我々がよく知っている古墳の森が出来るのです。そう考えると、今流行りの、何でもかんでも築造時復元と言うのが、地域環境にとって本当に良いことかどうか、考え直す必要があるでしょう。以上述べたように、1000数100年に渉って、石室が築造時そのままで保存されたのも、古墳が地域と密着した森になったのも、全ては「不透水層」のおかげだと言えるのです。これは高松塚やキトラ古墳などで、古代壁画が保存されてきたのも同じです。
(06/10/14)
技術士 横井和夫
1、始めに
闘鶏とは“つげ”という発音の当て字で、漢字そのものには何の意味も無い。“つげ”の語源は不明である。但し、この当て字はかなり古く既に日本書紀仁徳天皇略記に“闘鶏氷室”として現れている。
北摂地方の山地〜平野遷移部には古墳時代の遺跡が多数散在する。高槻〜茨木両市に渉る三島古墳群はそれらの内、最も規模が大きいものである。闘鶏山古墳は大阪府北部高槻市岡本地先にあり、古墳時代前期
(4世紀前半)の前方後円墳である。大阪層群の丘陵尾根を用いて築造されたもので、後期古墳のような濠や培塚などは伴わない。宝塚〜池田周辺では円墳又は方墳が多く、闘鶏山古墳のような大規模な前方後円墳は珍しい。後期になると今城塚古墳(6世紀後半)のような平野型の巨大墳墓が現れる。
最近、本古墳の後円部から未盗掘の竪穴石室が発見され、大きな注目を集めた。現地発掘の結果、地質学的及び土木工学的に見て興味を覚えるものが幾つかあった。その内次の
2点を紹介し、是非類似の情報があればお知らせ願いたいと思います
1 ,天井石と葺石の関係 2
,前方盛土の成層構造
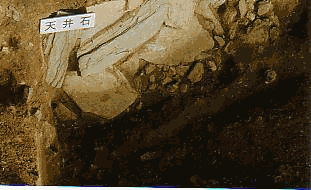 |
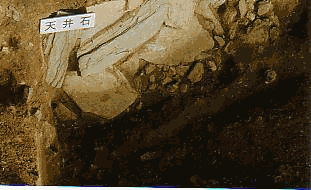 |
2 、天井石
天井石とは石室頂部を支える石である。横穴式古墳の場合は一枚岩が用いられる。本古墳は竪穴式なので石室の構造そのものが横穴式とは異なり合掌式になっている。従って、天井石そのものの規模は小さく、幾つかの板石の組み合わせである。見学会資料によると、「…天井石や側壁を構築する石材は、徳島県吉野川流域産の緑泥片岩が主体です」となっている。今回の発掘は一次調査だが、天井石は露出され、一部は標本として展示されている。但し、手で触る事は出来ないので、筆者得意の石を舐めるという技術は発揮出来ず、見かけでしか判断出来なかった。しかし、石質は間違い無く三波川タイプの塩基性片岩である。絹雲母が多く、三波川帯ではかなり産地は限定される。但し、似たようなものは舞鶴帯や三郡帯にもあるためこれだけでは産地を特定することは出来ない。
古墳に用いられている石材により、埋葬者の権威がどの範囲まで及んでいることを推定することは可能である。例えば兵庫県垂水五色塚古墳では前方部の復元に在来の葺石を用いている。葺石の材質は筆者が概観した限り全て領家型の変成岩であり、和泉層群の岩石は用いられていない。この点から被葬者の権威は淡路島北部までと推論される。
闘鶏山古墳では数カ所のトレンチがあり、葺石が露出している。観察出来た限りでは全て丹波帯起源の玉石である。

周辺の地質が大阪層群であること、古墳の近くには安威川の扇状地が発達することから、これらの石材は近くから幾らでも採取出来る。仮に被葬者の権威を示すために勢力圏内の石材を用いるなら葺石も同じ結晶片岩を用いるだろう。しかし、結晶片岩は石室の一部のみにしか用いられていない。この点から考えると、この石材は被葬者の権力を誇示するために実力によって集められたものではなく、別の意図を持ち、且つ入手方法もより平和的な手段、つまり購入によったのではないかと推論される。この点については筆者も結論的なものを言える段階には達していないため、幾つかの仮説を提示するに留める
1古墳の設計者が合掌式石室を意図し、それに合う石材として結晶片岩を選んだ。
合掌式石室の利点は梁に加わるモーメントが単純梁の
1/4になるという点である。合掌式を組み立てようとすると、岩塊状になる岩石よりは板状岩石の方が組み立てやすい。この結果、部材の断面が小さくなり、施工も楽になるので結果として工事費が安くなる。このために設計者が構造体として結晶片岩を選定した。しかし、これは直工費の話である。北摂から結晶片岩産地まではどのケースでも相当の距離である。運搬費を考えるとトータルコストとしては経済性に劣る。本説は説得性に乏しい。
2)被葬者が結晶片岩の使用を指定し、設計者はそれに応じて結晶片岩の特性を利用出来る工法として合掌式を選んだ。
結晶片岩という岩石は独特の雰囲気を持っている。特に雲母が多いとピカピカ光るので古代人はそれに何か霊的な力、神秘性を感じ被葬者が石室石材に指定した可能性はある。いわばオーダーメードである。しかし、結晶片岩は板状に剥がれるので大きな荷重が加わった場合に割れやすい。そこで設計者は断面力を低減出来る合掌式を選んだ。施主の注文であれば経済性を考慮する必要はない。従って、これはそれなりに説得力を持つ。
3)既に結晶片岩が高級石材として流通しており、被葬者も見栄を張った。
三波川結晶片岩のタイプ(模式地)は関東秩父盆地、多摩川の支流三波川である。ここで取れる石材は「三波石」と称し、江戸時代には高級石材として流通していた。昭和40年代後半、列島改造ブームに載って、あちこちで小金持ちが生まれた。金が出来ると、先ず家を建て、庭を造る。庭が出来るとそこに置く石が欲しくなる。この結果、銘石ブームというのが起こった。そこで狙われたのが紀ノ川、吉野川流域の川原に転がっている結晶片岩だったのである。結晶片岩を庭石に使うと金持ちの証拠になる。つまり、結晶片岩という岩石は昔から高級石材だったのである。但し、川原から石を持ち出すのはその後当時の建設省により禁止された。
本説は結晶片岩+合掌式工法が一つのビジネスモデルになっているケースである。例えば、古墳時代既に五條か大和上市辺りに石材販売会社があり、そこのセールスマンが「…オタクのような高貴な身分であれば、こういう石を使わないとこけんに関わりますよ。当社にお任せ下されれば他に負けないものを作って差し上げられます。つきましては設計・施工一切を当社にお任せ下さい」などと言葉巧みに被葬者かその親戚に売り込んだ。死後の世界の話をされると、大抵の人間は冷静では居られなくなり、「あとは任す」ということになる。現代不動産屋のセールステクニックが古墳時代に既に存在していたという仮説である。三島古墳群の中には古代埴輪工場と目される「新池埴輪製作」遺跡がある。古代石材製作工場が紀ノ川、吉野川流域にあってもおかしくない。
筆者個人としては第3)説に魅力を感じるが、これを証明するためには、類似工法が他に採用されているかどうかを確認することが必要である。そこで、是非、他にこのような工法があるかどうかの情報を教えてほしいのです。何故なら筆者はマルクスの向こうを張って古代には既に原始資本主義というものがあったのではなかろうか、そしてそれを支えていたのが古代の鉱山民、つまり地質屋ではないかという仮説を立てているのです。「新池埴輪製作」遺跡のようにある製品を集中して製作するということは、最小のコストで最大の利潤をあげるという資本主義原理以外の何者でもない。
3 、前方部盛土の成層構造
前方部でもトレンチが掘削されている。前方部盛土は
1.8m程度の小さなものである。下の図は断面の一部のスケッチである。
軸部 側部
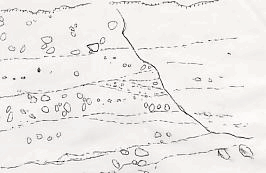
この断面では盛土は大きく軸部と側部の
2断面に別れる。両者の境界は1:0.3〜0.5位の急勾配斜面で側部が軸部の上に重なる。つまり、軸部の施工の後を追いかけるように側部盛土が行われたことを意味する。
軸部盛土の特徴は
0.2〜0.3m毎に成層していることである。これは1回毎の撒きだし厚を示す。現代の標準撒きだし厚は0.3〜0.5mが用いられるがこれは施工機械が大型化したためで、かつての標準は0.3mだった。つまり、現代の標準が既に古墳時代に確立されていたということである。しかも、それぞれが水平に成層している。極めて綿密な施工管理が行われていたことが伺える。
一方、側部では撒きだしの境界は判るが、軸部ほど厳密なものではない。軸部の盛り立てがある程度完成した後に一気に盛土した感がある。この盛り立て工法はゾーン型フィルダムの築造工法そのものである。軸部がコアに、側部がトランジッションに相当する。葺石がロック材に当たるのだろう。この技法はおそらく弥生以来の稲作農法に由来するだろう。つまり、古墳の築造には従来の農業土木技術特に築堤技術がそっくり応用されているのである。
4、これらから何がいえるのか
これまで述べてきたことから、前方部築造は農業技術、後円部石室築造は鉱山技術の応用であると言えよう。古墳は中央地下に玄室を有する。これは一種のトンネルであり、地下世界を表す。これの築造には横穴であれ、竪穴であれ地下世界を支配する鉱山民の技術が必要である。一方それを覆う墳丘の築造には土を動かし管理する技術が必要である。これは農耕民の世界である。一般に農業と鉱山とは互いに敵対する関係にある。しかし、ここでは両者が融合している。日本古代史のある時期に両者は和解し協調する関係に入ったと考えられる。筆者は大和三輪大社がその象徴と考えている。
しかしながら、両者の協調関係は何時までも続かなかった。人口に勝る農耕民の力が圧倒的になり、鉱山民は歴史の闇に押し込められるようになる。日本史に於ける鉱山民の不当に低い評価がその証拠である。鉱山民の歴史を発掘することにより、もう一つの日本史が描けることが期待できる。
筆者らの世代が中高生の頃の日本史教科書はマルクス流唯物史観が主流で、古墳時代は古代奴隷制社会で古墳の築造は多数の奴隷労働によるものだった、とされていた。闘鶏山古墳で見るように、合掌式石室や積層盛土等高度な土木・建築工法を選び、重要部分の材料はそれに合ったものを遠隔地より運搬している。これはとても単純な奴隷労働で出来るものではない。周到な設計・施工計画、綿密な施工管理があって初めて可能なのである。古墳の築造は奴隷労働のような労働集約型事業ではなく、高度な技術集約型事業と考えられる。少なくとも古墳時代前期にはそれを可能にする技術が完成されており、それを請け負う技術集団が形成されていたと言える。マルクス流唯物史観こそが間違いの基だったのである。(終わり)
以上