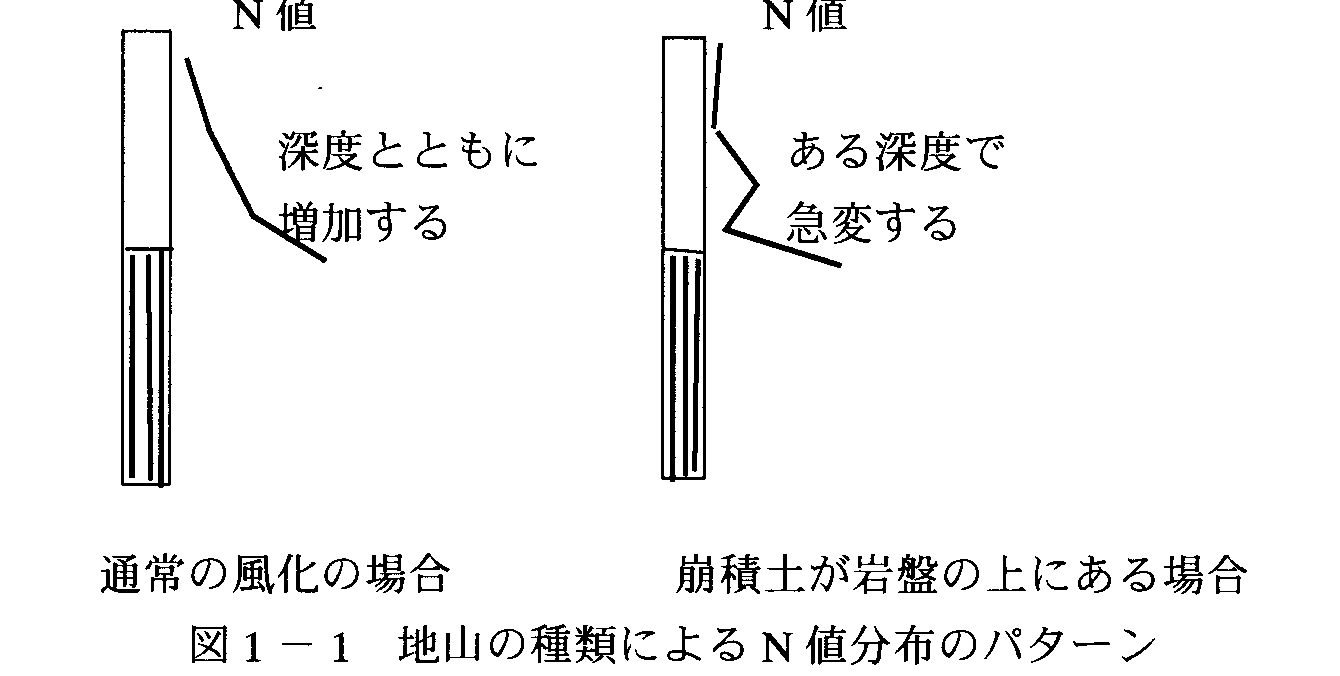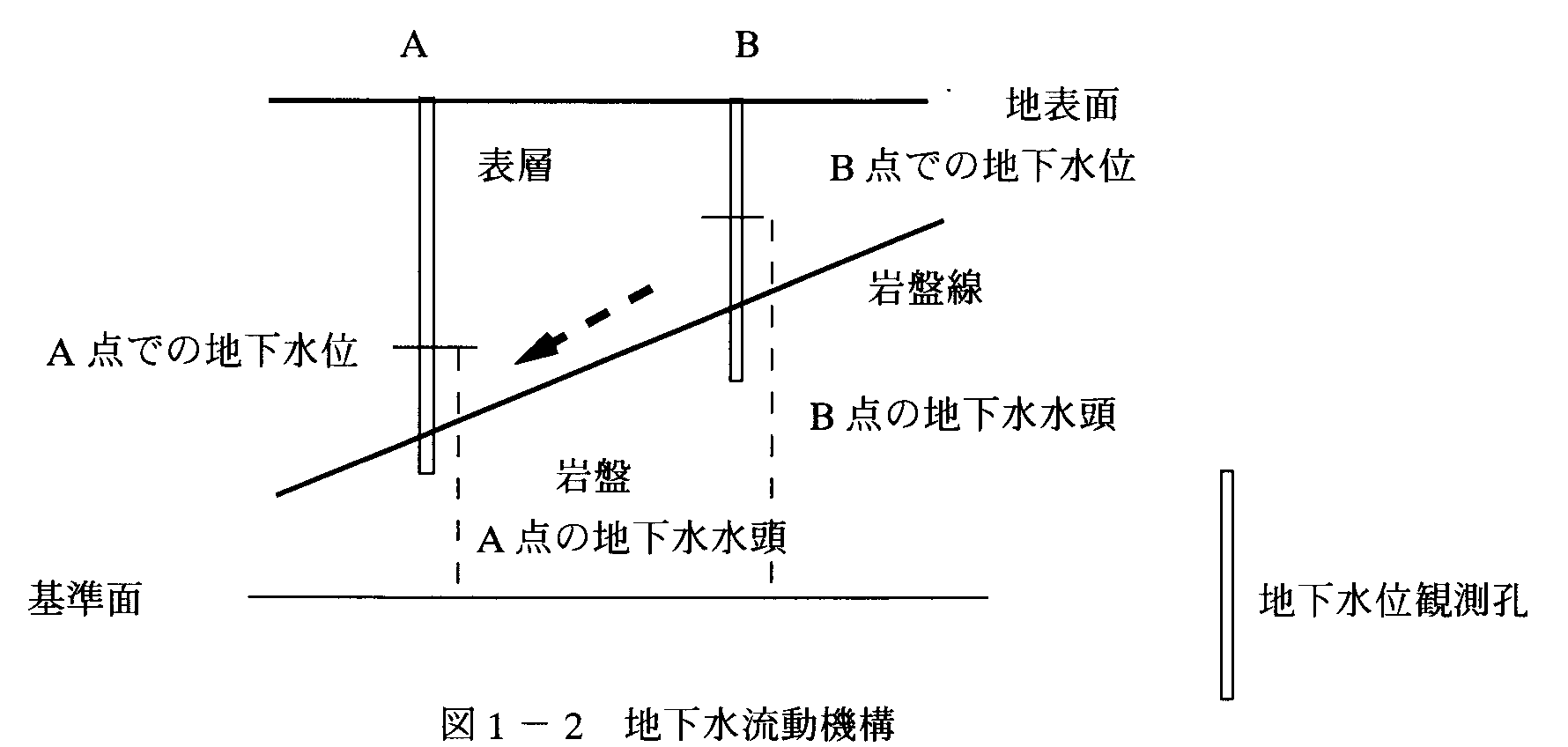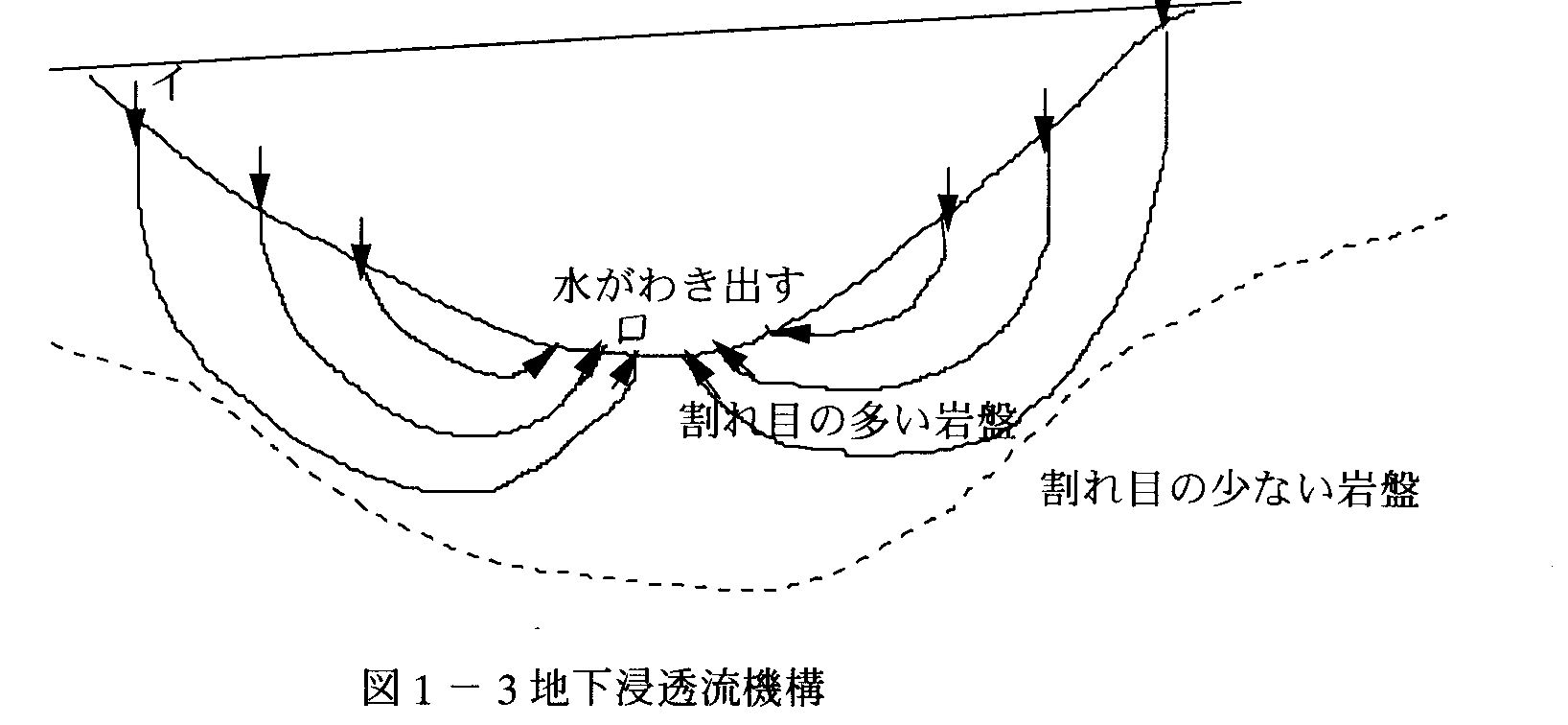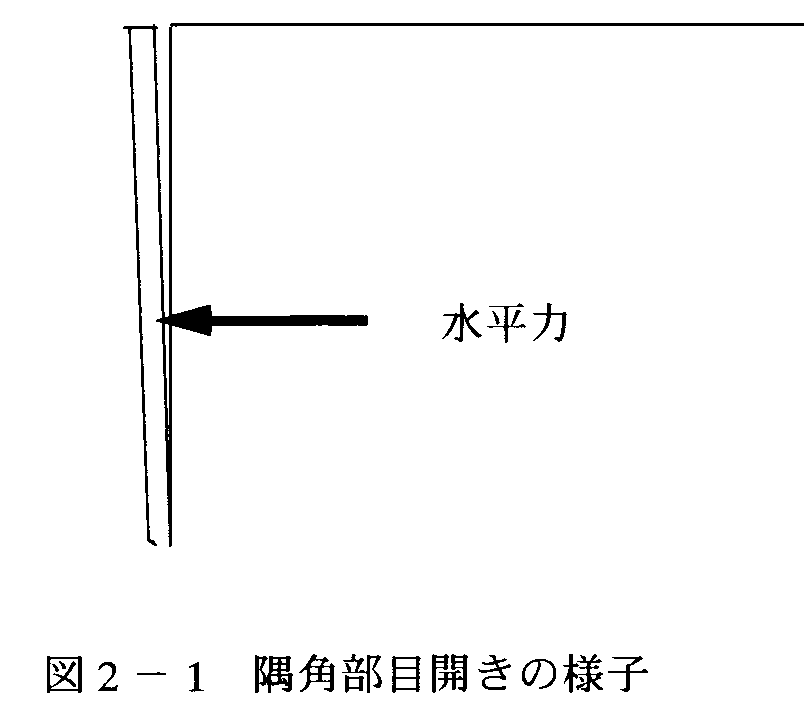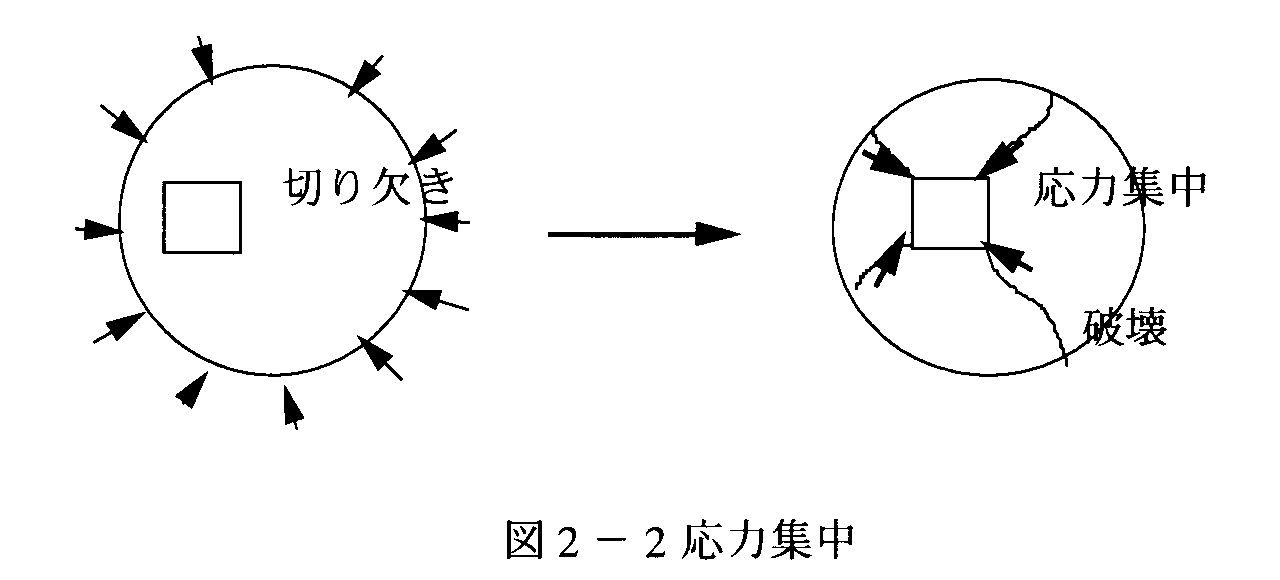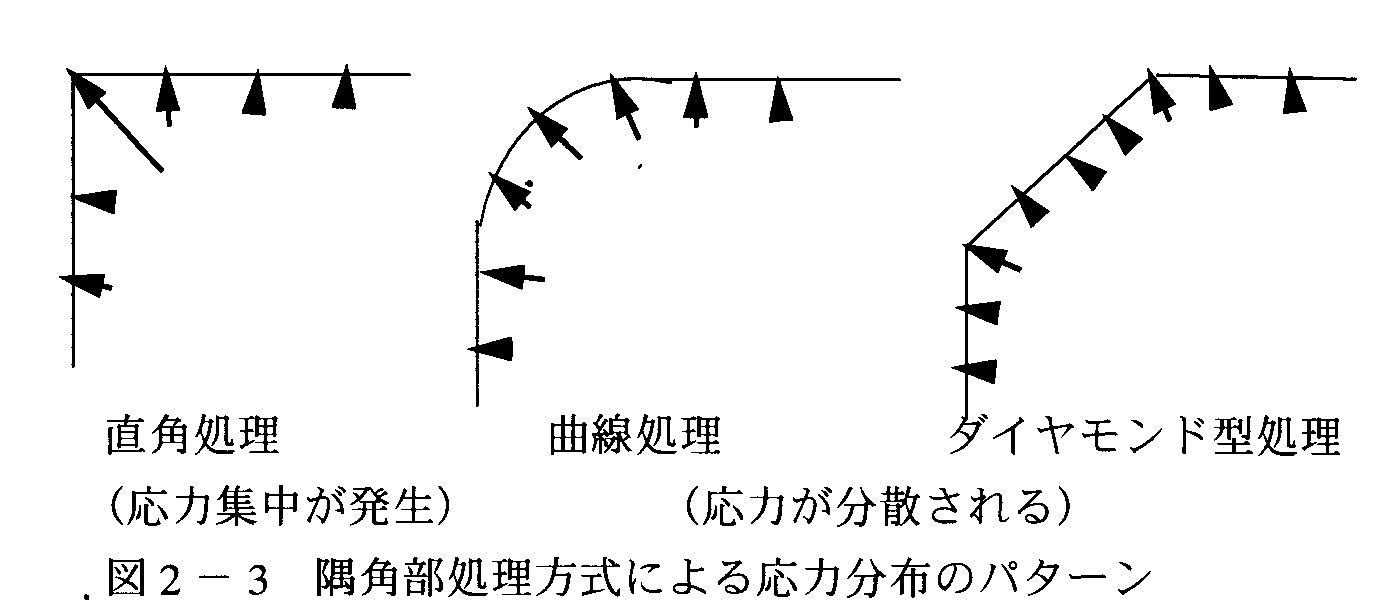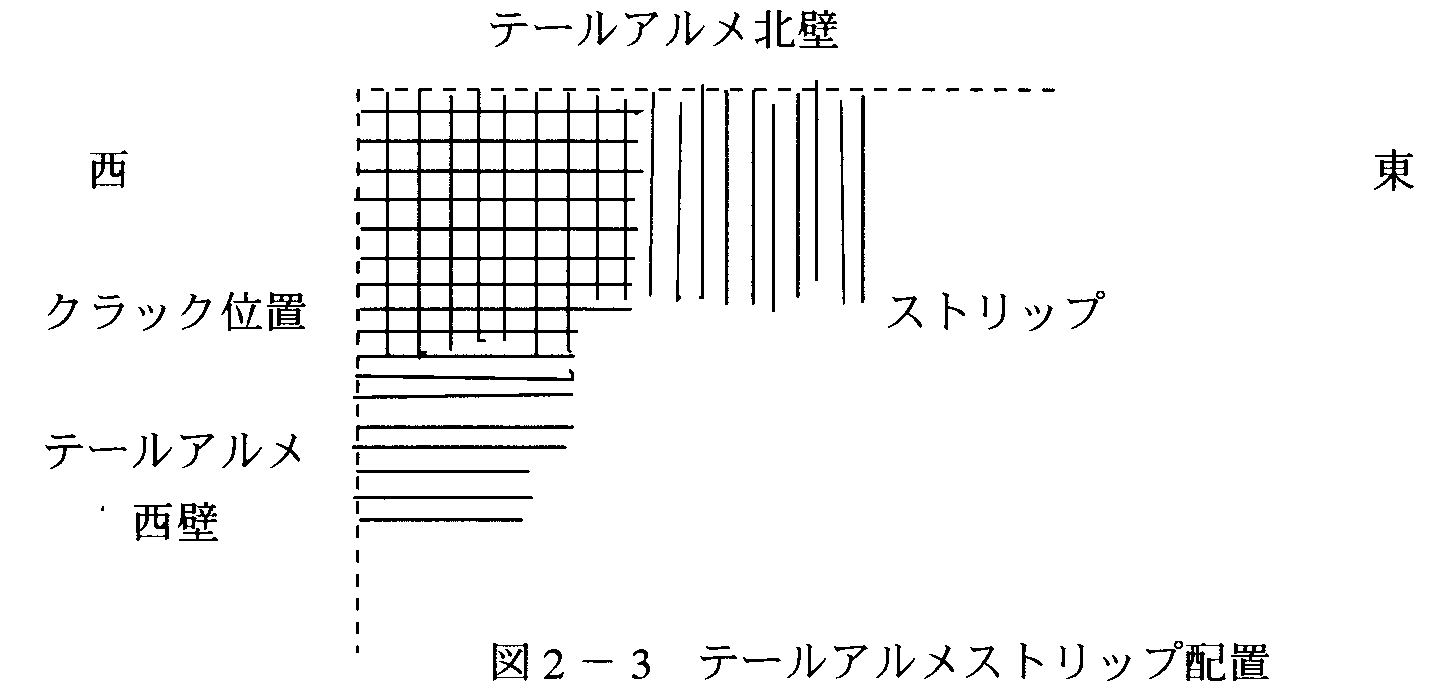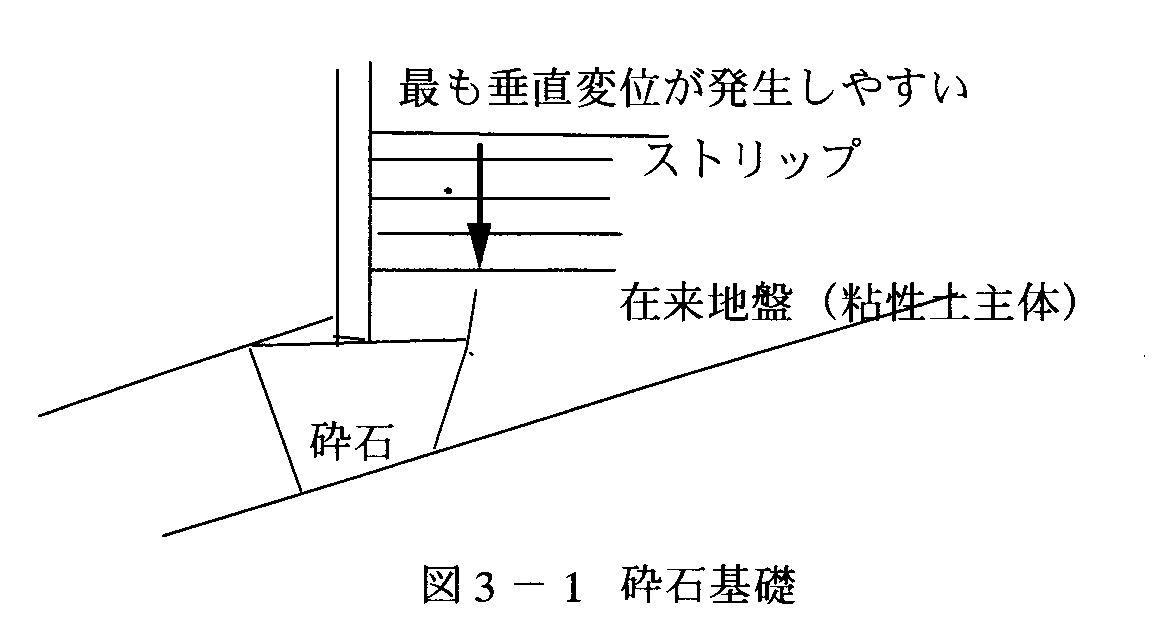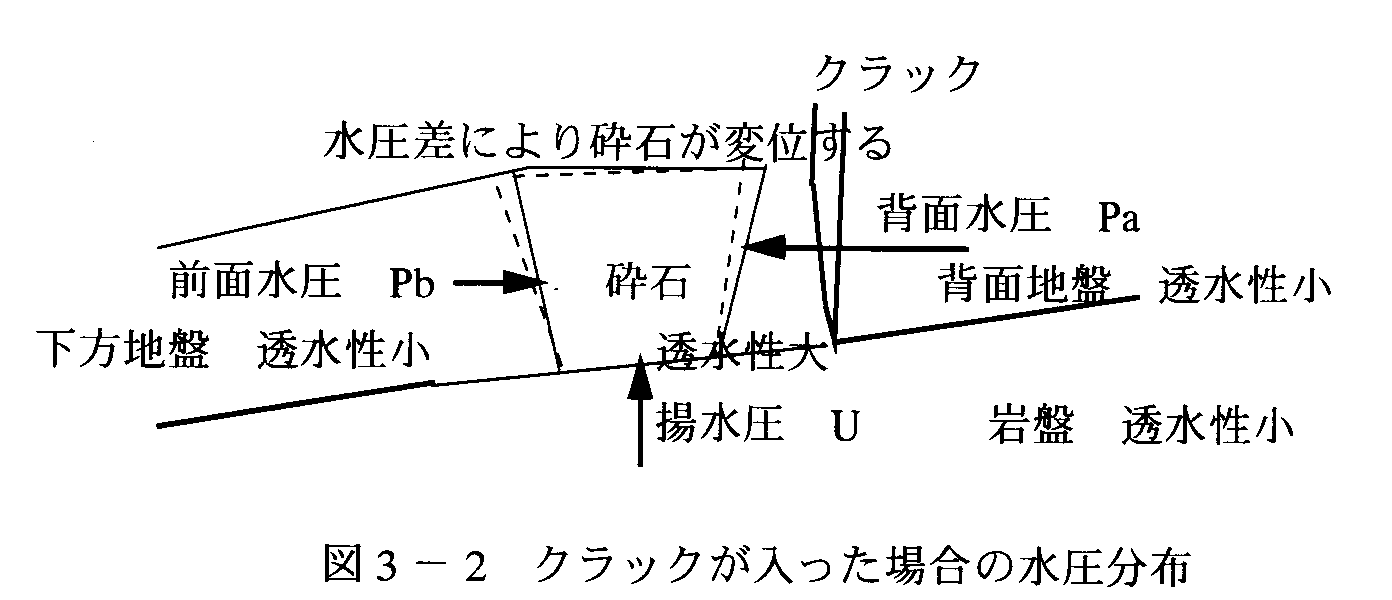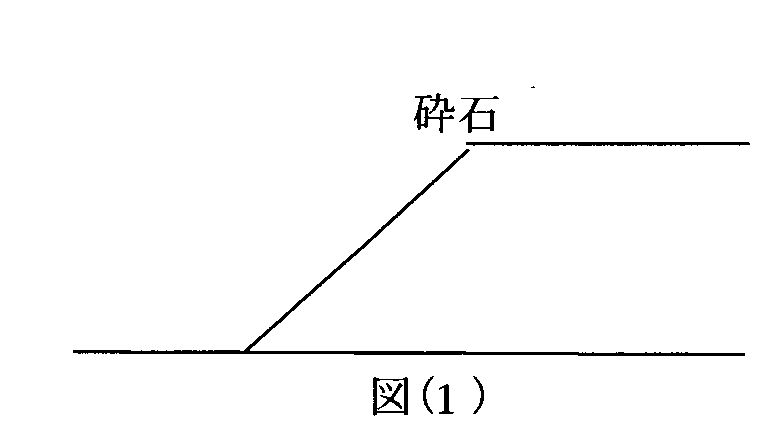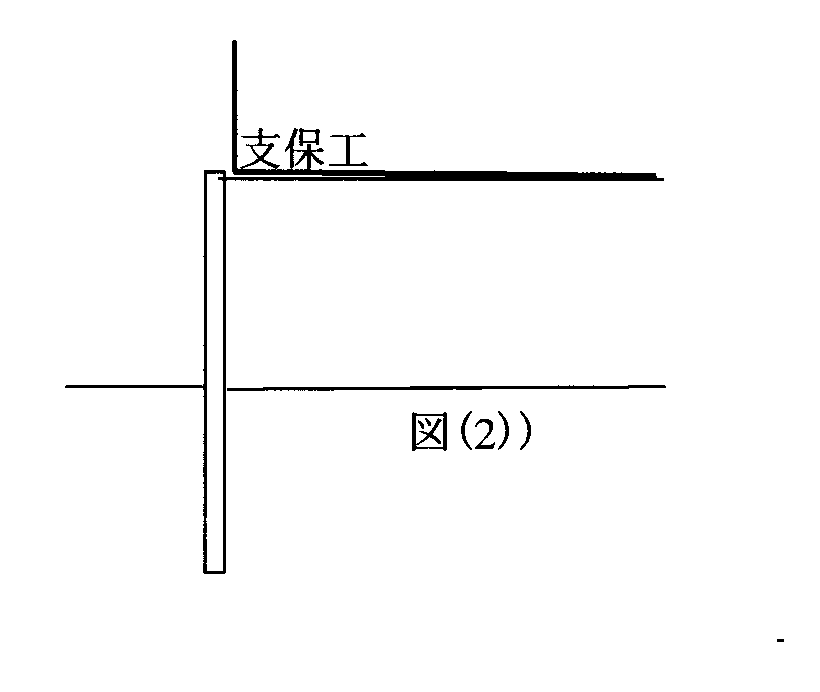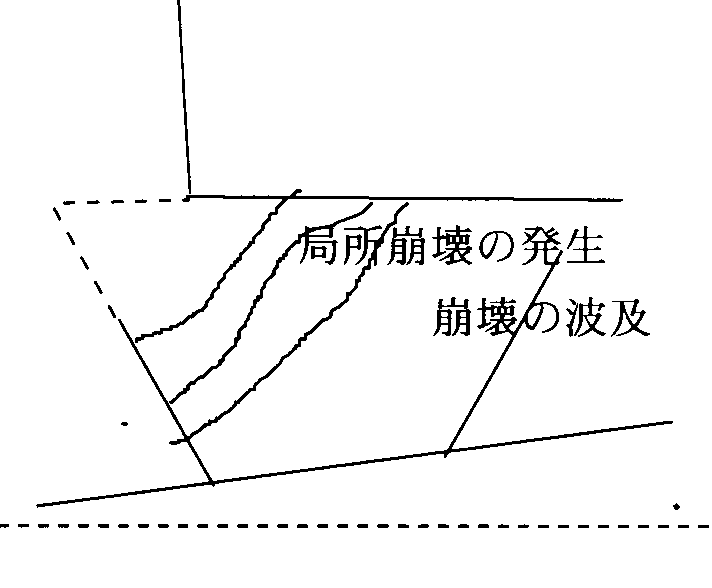控訴人Aに対する照会事項の回答
技術士(応用理学部門) 横井和夫
1、照会事項1について
(回答) テールアルメ崩壊事故前後に行われた10箇所のボーリング調査結果(丁第7号証の1〜10)、及び2箇所のサウンデイング調査結果(丁第8号証の1〜4)を根拠にしている。
(回答理由) 本照会事項は1、斜面下の土質は一体何物か、2、地下では水はどのように流れるのか、を明らかにすることを求めているものと思われる。
1−1)1、について 菊池鉄工所滋賀工場の基盤になる地質を構成するものは、新第三紀鮎川層群と呼ばれる地層である(甲64号証p3)。これは本地域では主に、泥岩・砂岩・礫岩からなる。それを覆って局部的に
1)沖積層
2)崖錐(崩積土)
3 )段丘層
という新しい地層が分布する。
1)沖積層は現在の河川の流域にしか分布しない。当該斜面周辺では、斜面下方の水田の下にのみ見られる。3)段丘層は、岩盤を覆って丘陵外周に発達する平坦面(鑑定書図7−1で示した段丘面)下にのみ分布する。これら以外の土砂は2)崖錐(崩積土)ということになる。
本斜面では、地表面下10m近くにわたって、岩盤の上に軟弱な土質が分布する。これが崩積土である。一例としてテールアルメ直下のB−NO4地点(丁第7号証の4)を採り上げる。本地点での土質構成は概略次のように纏められる。
| 深度(m) |
土質 |
N値 |
備考 |
| 0.0〜3.5付近 |
砂質粘性土 |
2〜3 |
(A)崩積土 |
| 3.5付近〜5.5 |
同上 |
9 |
| 5.5〜8.5 |
礫混じり砂質粘性土 |
7〜13 |
| 8.5〜9.6 |
粘土質砂 |
4 |
| 9.6〜10.7 |
砂質粘性土 |
13 |
鮎川層群の風化帯? |
| 10.7〜 |
砂岩 |
50以上 |
鮎川層群 |
崩積土と岩盤との境界は浅く見積もっても9.6mである。ボーリング地点標高は判っているから、これから崩積土と岩盤境界との深度を差し引くと、崩積土と岩盤境界の標高が求まる。
(例;B−NO4地点) ボーリング標高(m) 境界深度(m) 境界標高(m)
TP301.54 9.6
301.54−9.6=291.94以上の操作をボーリング各地点で繰り返す。
求められた境界標高を平面図上にプロットし、その等高線を描けば、鑑定書図9−1に示した岩盤等高線が自動的に得られる。
|
〔(A)を崩積土と判定出来る理由〕
(1)深度10.7mまでは粘性土が主体の不均質な土質からなっている。N値は平均すれば上部で2〜3、下部で10前後である。これは一般にいう沖積層(例えば、大阪平野の地下を作る最も新しい地層)のそれと変わらない。
(2)段丘層は数万年〜10数万年前に堆積した地層であり、N値は通常30〜50を示す。従って、段丘層であるとは考えられない。
(3)深度10.7mを境にN値が急変する。丘陵を構成する鮎川層群は新鮮部ではN値50以上あって当然であるが、風化が進むと土砂化するので相対的に低いN値を示すことはある。しかし、それは山頂部に限られ、斜面部では風化部は浸食されるので、 厚い風化帯が残ることはない。せいぜい1〜2mのオーダー(程度)である。又、 風化の場合、N値は深度と共に増加することが普通で、ある深度を境に急に大きく なることはない。従って風化岩でもない(下図参照)。
図 1−1 地山の種類によるN値分布のパターン
( 4)土質は緩い雑多な土砂の集合体であり、他地点との連続性は認められない。沖積層・段丘層の場合、必ず何らかの連続性がある。 |
鑑定書図9−1を見ると、
(1)岩盤等高線(図の紫色の線)はテールアルメ隅角部では、北東−南西方向に平行に配列している。
(2)西側(図の右側)では、岩盤等高線間隔は粗くなって一つの台地を形成している。
(3)岩盤等高線はテールアルメ北側(図の中心部)では大きく湾曲し、テールアルメ崩壊部から真っ直ぐ 北に伸ばした線を取り囲むように配列している。これが地下の谷状地形である。
地表面標高(地形の等高線で表される)と岩盤標高(岩盤等高線で表される)との差がその地点での崩積土の厚さを表す。地表面の等高線は岩盤等高線と無関係に平行に配列している。当然、地表面と岩盤等高線との差は上で述べた岩盤の谷状地形の部分で最大になる。つまり、テールアルメ崩壊部直下の下方斜面部で崩積土が他より厚くなる。照会事項
1、の「崩壊部直下に厚い地すべり崩積土が堆積していた」といえる根拠は以上のとおりである。
1−2)2、について
陸上に存在する水を海水と区別するために、「陸水」と呼ぶ。陸水の起源は言うまでもなく雨である。山地に降った雨は斜面に沿って谷に流れ、川に合流する。つまり、谷こそは雨が最初に集まる場所である。実は、地下でもこれと全く同じ現象が起こる。しかし、そのメカニズムは少々複雑である。
①降雨があると、雨の大部分(地表条件によってかなり異なる。本件現場では7〜8割程度か)は地表面に沿って流出する。残りが地下に浸透する。
②降雨前の地下水位が低い場合、地下水位より上の土は土粒子・粒子表面の水分・空気の3者からなっている。浸透してきた雨水は空気を追い出しながらゆっくりと地下に浸透してくる。(この過程を「不飽和浸透」と呼ぶ)
③雨水が岩盤まで到達する。水の通り易さを表す指標を透水係数と呼ぶ。岩盤の透水係数は通常、土の1/100〜1/1000以下である。つまり、集中豪雨のような短期的な降雨では岩盤に直ちに浸透する水は全体の極く一部に過ぎない。
④従って、浸透してきた水の大部分は岩盤表面に滞留し、地下水面を形成する。
⑤更に地表からの水の供給が継続すると、地下水位は上昇し出す。
一般に地下水位の上昇は降雨より少し遅れて生じるのはこのためである。
⑥ここで、岩盤表面が傾斜している場合を考えて見よう。
降雨が始まってある時間が経過した後、異なる 2点A、Bで地下水位が観測されたとする。ある基準面を考える(何処でも良い)。地下水位と基準面との差を地下水頭と呼ぶ。A、B両点は岩盤までの深さが異なり、浸透水が岩盤に達する時間も異なる。当然地下水位も地下水頭も異なる。岩盤が深いA点の方が地下水位が当然深くなる。
地下水水頭は水の位置エネルギーを表す。この場合、「エネルギー保存の法則」により、全体の地下水頭分布を均一化しようと水が動き出す。つまり、当初水頭の高い
B点の地下水位は下降しようとし、低いA点の地下水位は上昇しようとする。しかしながら、B点は岩盤が浅いから水は直ぐには下に浸透出来ない。普通はA点では水はわき出して来ないと思う人が大部分であろう。しかし、実はA点でも水は湧いて来る。但し、その速度はB点での地下水位低下よりは遅れる。その理由は次に述べる通りである。この結果、B 点からA点に向けて地下水の流れが生じる(図中矢印)。
図 1−2では、岩盤に浸透する水は無視し、崩積土中に滞留した水の動きのみを示している。一般には、岩盤に浸透する水の量はごく僅かだからである。しかし、岩盤の中でも割れ目の多さによって水の通し易さが異なる。割れ目の多い部分は水を通しやすく、場合によっては土と変わらない透水性を示す事がある。このような部分は一般には岩盤表面近くか、又は断層破砕帯の近くである。 岩盤の谷状部の岩盤状況が下図のとおりであったとしよう。ここに雨が降って、水が地下に浸透する。
図でイの点に達した水の内、大部分は図 1−2で示した機構に沿って谷に向かって流れる。しかし、一部は岩盤中に浸透する。岩盤の下部に割れ目の少ない岩盤があると、浸透した水はその下には浸透出来ないので、図の流線に沿って岩盤表面に環流してくる。結果として谷底部分には水がわき出してくるのである。但し、水が流れる距離は長くなるので、到達時間も長くなる。
崩積土の透水性が低い場合には、岩盤表面に環流してきた水は崩積土中に浸透出来ないので、崩積土底面に水圧を発生させる。この水圧は地すべり規模が小さい場合、馬鹿にならない大きさになる。この結果、崩積土の剪断強度が低下し、地すべりを発生させるのである。
一般に、降雨直後に発生した崩積土地すべりは殆ど上記の経過をたどる。
つまり、本斜面は地下の岩盤の中に谷状地形が存在するため
1) 浸透してきた水が岩盤の表面に沿って谷に向かって流下する。
2) 岩盤に浸透してきた水が谷に向かって環流する。
の2点から、2重の意味で地下水が集まりやすい地形であると云える。
もし、地下地形が谷状を示しておれば、地下水も谷に向けて流れるのである。これが、本斜面が「地下水が集まりやすい条件を作っていた」と考えられる理由である。鑑定書図9−1に水色破線で示した「想定される水の流れの方向」は、上記に基づく地下水の流れを表している。
2、照会事項2について
(回答)
1、被控訴人ヒロセが丁13号証で主張している、①阪神大震災で垂直変位が発生したという見解、②西側壁面及び隅角部に発生した目開きが垂直変位によるものであるという見解、のいずれも事実の裏付けのない非合理的なものであり、容認出来ない。
2、隅角部目地開きの原因は(1)壁高が大きすぎる、(2)隅角部処理を直角で済ましたことにある。
何れも、大学教養程度の初等物理学の知識があれば自明である。
(回答理由)
本照会事項の要点は
1、西側壁面及び隅角部に発生したクラック及び目開きが阪神大震災を原因とする垂直変位によるものといえるかどうか。
2、目開きの原因をどう考えるか。
の2点にまとめられる。
2−1)1、について
この問題は、被控訴人ヒロセによる丁13に対する所見(平成14年1月15日付け書面甲第62号証)で詳しく述べてあるが、ここで再度要点をまとめる。
1)震源位置から見て、本崩壊位置に垂直変位を生じるだけの地震時鉛直力が作用することは考え難い。
2)地震直後ではテールアルメ頂部コンクリートには変状は認められない(丁11−1)。5月12日集中豪雨後で明かな変状が認められる(丁11−2)。
3)一審段階で、被控訴人ヒロセは垂直変位には何ら言及する事はなく、具体的な証拠も示していない。平成11年9月22日証人尋問でのヒロセ高見証言があるのみである。これも証拠に基づかない推測に過ぎない。
隅角部目開きの証拠としては被控訴人の一人菊池が提出している乙1号証の1、2しかない。しかし、これは平成6年3月19日撮影で地震とは無関係である。これが地震で、より開いたという前提で、以下「隅角部目開きが何故生じたか(地震でより開いたか)」について検討する。
注;これまでの被控訴人A、Dの主張をみていると、垂直変位とは、丁11−2(平成7年5月26日撮影)に見られる壁体の変状のことを指しているのではないかと思われる。そうだとすると、これが地震後に生じたということになる。実は、これが被控訴人側主張の最大論点になる。 ところが、地震直後の丁11−1(平成7年1月27日撮影)には、何ら変状は認められない。当鑑定人は地震発生直後に震災地域を調査した経験を持つ。その経験から 言うと、地震直後の被害はたいしたことはなくても、それがその後拡大していったケースは確かに多く見られる。しかし、その原因は地震が発生した週の後半に到来した低気圧による降雨、3月以降の降雨、それに対策の手遅れである。地震発生時に何 事もなく地震発生から4ヶ月も後にいきなり地震変動の影響が表れるということは、 少なくとも地表レベルでは無いのである。本崩壊部では、5月12日に日降雨量231㎜という強い集中豪雨がある。丁11−2 はこの後に撮影されたものである。この段階で、テールアルメ下方斜面の地下水位が
急上昇し地すべりの初期段階に達し、その影響が壁体に現れたと考えることが合理的である。 被控訴人B、Dは地震により発生する垂直変位と、地すべりによる構造物・地盤変状の判別が出来ないのだろう。 |
本証拠では、目開きが壁の上に向かって大きくなっている様子が見える(図2−1)。
こういう現象は、上図のように壁体のやや下方に設計以上の水平方向の力が働かなくては生じない。なお、こういう現象が発生してもテールアルメの設計原理より、安定性には何ら影響しない(壁体上部のストリップ定着長が1〜2㎝短くなるだけである。この程度の誤差はテールアルメの安全率の中に含まれている)。垂直変位の場合は基礎の一部が不等沈下したことになる。このときも目開きは生じるが、上図のように上に向かって大きくなると言うことはない。大体同じような幅になるか、斜面上であることを考慮すると下段の方が大きくなる可能性の方が高い。以上から、垂直変位が発生したという見解自体疑わしい。従って、クラック、目開きの発生原因は別に求めなければならない。
2−2)2、について
隅角部目開き・テールアルメ西壁にクラックが入った原因について当鑑定人は地震の影響を否定してはいない。この点について、鑑定書では説明不足があったかもしれないので、補足説明を行っておく。
手に竹を持って揺らしていくという実験を考えて見る。竹が短いか長いかで揺れ方が異なる。短い場合は、あまり揺れない。長い場合は暫く揺らしていくと次第に揺れは大きくなり、その内、竹が勝手に揺れるようになる。この現象を「自由振動」と呼ぶ。自由振動を起こすかどうかは、揺らしていく周期と竹の持つ固有振動数及び竹の長さとの関係で決まる。揺らす周期と竹の固有振動数が一致し、竹がある長さ以上あれば大きく揺れるし、一致しなかったり短い場合は揺れは小さいか、揺れない。
長さが同じで竹よりも太い丸太を同じように揺らして見よう。竹と同じようには揺れないか、又は全く揺れない。この差は竹と木の材質(正確には弾性係数E)と断面積(正確には断面2次モーメントI)、長さの関係から生まれる。EとIの積を曲げ剛性(EI)と呼ぶ。EIが小さければ曲がりやすく、大きければ曲がりにくい。弾性係数と物体の密度から固有周期fが決まる。固有周期とは、その物体が最も揺れ易くなる振動数である。固有周期が決まれば固有の波長λが決まる(λ=1/f)。ある振動を与えたとき、物体には波長λの波が発生する。物体の長さLがλより大きければ、物体は大きく揺れる。しかし、Lがλより小さい場合は全く揺れないか、揺れても大きくはない。
つまり、振動が加わった時の物体の揺れ方は(1)物体の材質、(2)物体の断面積、(3)物体の長さ(建築物では高さ)に関係する。なお、例で挙げたように物体の一端を固定して物体に力を加える状態を「片持ちバリ」という。地震時でもこれと全く同じ現象が起こる。
(2−2−1)隅角部について
隅角部ではテールアルメの部材は側方からの拘束が無いため、上の例での竹(片持ちバリ)を揺らした状態になる。又、壁高も14mに及ぶ高いものであり、共振を起こした可能性が高い。共振を起こしても、地震が終われば壁は又元の位置に戻る。従って、目開きが発生するはずはない、と一般には考えられる。
しかし、この場合、後ろに土がある。竹と土では揺れ方に差がある。土も地震時では竹と同じように揺れるが、竹と同じようには戻れない。つまり、地震が終わった時の竹と土では静止した位置に差が出来るのである。更に、隅角部には応力集中という要素が加わる。応力集中とは、不連続な部分を持つ物体に均等な力を加えると、不連続部に力が集中するという現象である。例えば、図2−2のように中に四角形の切り欠きを持つ円盤に力を加える。すると、切り欠きの部分に応力が集中し、最期には円盤そのものを壊してしまう。つまり、どんな物体も周りとは違う形や性質を持ったところがあれば、必ずそこに応力集中が生じる。
本件テールアルメでは隅角部は直角で処理されている。明瞭な不連続部である。図2−2の例から隅角部に応力が集中するのは当然である。周囲との応力の差が隅角部図2−1で示したような上に行くほど大きくなる目開きの原因になっているのである。隅角部を図2−3に示すような曲線処理なりダイヤモンド型で処理すれば、応力は分散されるので、目開きの発生を防げた可能性は高い。
(2−2−2)西壁部
次に西側壁面クラックについて考えてみる。西側壁面クラックでは、地震直後の写真そのものが提出されていないので、どの位置でどのようにクラックが入っているか、全く判らない。本当に入っていたのかどうかも疑わしいのである。しかし、一応壁体の何処かに入ったと考える。ここでも、地震時では隅角部と同じような現象が発生する。
この部分で注意しておかなければならないのは次の2点である。
(1)隅角部では、テールアルメ隅角部処理のため、ストリップが2段配置になっている。つまり、外側の範囲よりストリップ密度が2倍になっており、地盤の剛性が他より大きくなっている。こういう場所に同じ地震動が作用すれば双方で揺れ方が異なるのは当たり前なのである。これは上の例での竹と丸太の違いである。
(2)壁高が短距離で急速に変化する。
北壁ではクラックは入っていない。その理由としては、北壁では壁高が10m前後で大きな差はないことが挙げられる。一方西壁では僅か30m未満の間で壁高が14mから3.6mまで変化する。壁高の大きい箇所は共振を起こし、低い箇所は揺れが小さい。これは先に述べた、竹の長さで同じ振動でも揺れ方が異なるという例に相当する。西壁各所で異なる地震時挙動を発生するには十分な変化である。
(2−2−3)結論
以上、述べたことを纏めると隅角部目開きは
①壁高が大きく、壁体が地震動と共振を起こした可能性がある。
②壁体と裏込土の固有周期に差があり、地震終了時のそれぞれの変位に差を生じた。
③隅角部処理が直角であるため、過度の応力集中を生じた。
又、西壁クラック発生原因については
④西壁の高さが短距離で大きく変化するため、壁体各部での地震時変位に差を生じた。
⑤隅角部ではストリップが2重に配置されているため、他の部分とは地震時の挙動に差を生じた。
を原因と考えることが妥当である。
3、照会事項3について
(回答)
垂直変位が生じた場合、基礎を砕石で置き換えたとしても、本件で崩壊を防ぎ得たとは思えない
(回答理由)
ここで言う垂直変位とはテールアルメ基礎地盤に発生した垂直変位と理解する。
この問題は次の2点に分けて考える必要がある。
1)内的安定
2)外的安定
1)内的安定
これは砕石置き換えをしてもしなくても関係は無い。そもそも、テールアルメは可撓性構造物であり、目に見えないような変位が発生しても安定性が損なわれる事はない。内的安定を決定する最大要素は、ストリップの状態である。ストリップが設計強度を維持し、定着長が設計条件を満足しておれば良い。仮に10㎝の垂直変位を生じたとしてもストリップがそれで切断されることはない。単に曲がるだけである。曲がり方が急であれば、表面の錆止め塗装が剥がれ、そこから腐食が進行し長期的には切断するケースもあり得る。しかし、半年程度でそのようなことになることはない。もし半年程度で腐食が進行するようであればメーカー側の品質管理に問題がある。垂直変位により、定着長は確かに若干短くなる。しかし、10㎝程度定着長が短くなったとしても、それが直ちに安全率不足に結びつく事はない。そもそも、テールアルメの設計はその程度の変状は十分吸収出来るだけの安全性を見込んでいる。つまり、内的安定については垂直変位は何ら問題にならないと云える。
2)外的安定
在来地盤はN値が2〜3に過ぎない粘性土に対し、砕石は十分高い剛性を持つ。その結果、同じ地震動に対しそれぞれで揺れ方が変わるので、地震時での変位の差は砕石と在来地盤との境界付近に集中する。その結果、垂直変位が発生するとすれば、砕石と在来地盤との境界付近と考えるのが妥当であろう。
被控訴人ヒロセはこの結果が地盤のクラックに発展したと主張する。クラックが入った場合、最も問題になるのは水である。クラック周囲の地盤の透水性が高い場合は、水がクラックに浸透しても直ぐに排出されるので問題はない。しかし、透水性が低い場合は、水は直ぐには排出されないのでクラック内に滞留する。更に水が供給されると水圧が発生する。これはクラックの大小に関係はない
当初設計で考えられている基礎構造は模式的には図3−1の通りと考えられる。
図3−1で考えて見よう。ここで、砕石は透水性の高い地盤、周囲の在来地盤はp−1の表1−1を見ても判るように透水性の低い地盤である(土質が粘性土故)。地震で砕石の直ぐ裏側にクラックが入り、降雨により、そこに水が浸透してくるとしよう。砕石は透水性が高いため、クラック内の水は砕石内に浸透する。この段階で降雨が終われば、砕石内の水はゆっくりと周囲の地盤に排出されるので、水圧は発生しない。しかし、集中豪雨のように大量の水が短時間に供給された場合、在来地盤の透水性が低いため砕石内の水は直ぐには排出されず、高い水圧を発生させる。
この水圧は当然、砕石の背面及び底面に作用する。水圧が大きくなれば、砕石で置き換えていたとしても危険な状態になることは十分予想される。
又、1回目の降雨で崩壊を免れたとしても、背面水圧Paより、前面水圧Pbの方が小さいため、この差により、砕石自身が必ず変位する。砕石は水位が低下すれば、又元の位置に戻るが、下方地盤は元の位置に戻れない(これは、砕石と在来地盤の剛性に差があるためである)。この結果、砕石と下方地盤の間にも新しいクラックを作る。
次の降雨があると、新しいクラックにはまともに水圧が作用することになる。もし、下方地盤が地すべり性であった場合、この水圧がすべり面に作用するので、新しい地すべりを発生させる。こうなると、前面の押さえがなくなるので、まず砕石に局部的な崩壊が発生する。これが周囲に順次波及する。従って、砕石の有無に関わらず、テールアルメは崩壊する。仮に砕石の変位が無視出来るとしても、図3−2では、背面水圧Paが下方斜面の在来地盤に直接作用する事になる。在来地盤が地すべり性であれば、水圧はすべり面に直接作用することになるので、結果は同じである。
鑑定安定解析では次のような結果を得ている。
|
摘要 |
ケース |
すべり安全率 |
| 無処理 F1 |
砕石置換 F2 |
| 全体すべり |
地下水位考慮 |
0.947 |
1.001 |
| 地下水位無視 |
1.371 |
1.433 |
| 局所すべり |
地下水位考慮 |
1.001 |
1.163 |
| 地下水位無視 |
1.218 |
1.401
|
ここで、局所すべり、地下水位考慮、砕石置換のケースが上記条件にほぼ該当する。この時の安全率はF2=1.163<1.20で必要安全率を満足しない。これだけで明かな設計ミスである。又、計算に用いた地下水位が崩壊後時間を経過したものである点から崩壊時地下水位は更に高く、従って崩壊時安全率は更に低かったものと容易に想像出来る。従って、砕石置き換えは基礎改良として何ら効果は無いと云える。
(以上)
| (砕石が局所崩壊を起こすメカニズム)
砕石基礎は要するに基礎を砕石で置き換えただけのものである。砕石を盛り上げようとすると、垂直に盛土出来ず必ず図(1)のように傾斜がつく。どうしても垂直に盛りたければ図(2)のように支保工で支えなくてはならない。
この上に荷重物を載せる。支保工には
①砕石の自重による水平荷重
②載荷重による水平荷重
の合計が作用する。
支保工の耐力がこれより大きければ全体は安定する。しかし、支保工が壊れたり、支保工を外したりすると砕石は端部から崩壊し出す。ここで、支保工の役割を果たしているのが斜面下方の在来地盤である。これが地すべりを生ずれば、砕石基礎も崩壊してしまうのである。鑑定書p−5〜6に述べてあるように、 砕石基礎は外側地盤の安定性が長期的に確保される場合以外には用いてはならないのはこのためである。 |
その6へ